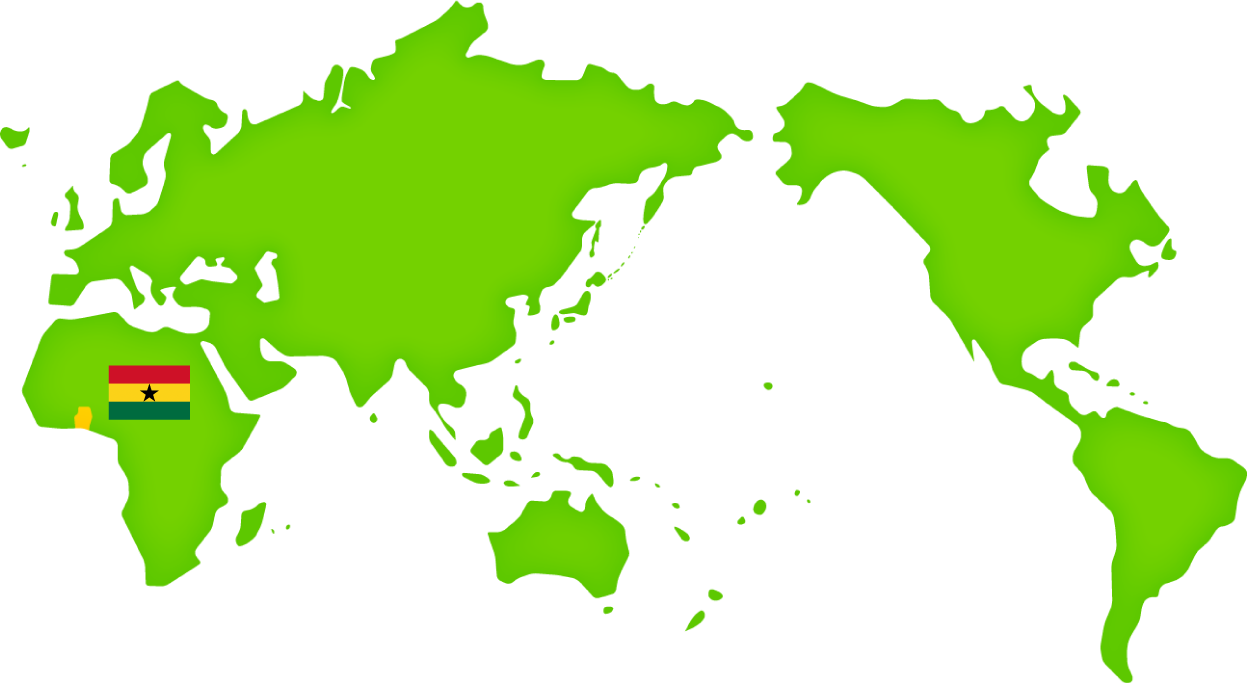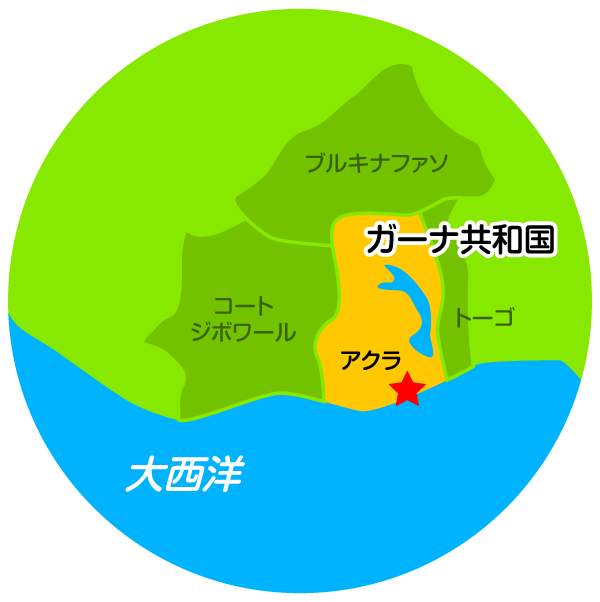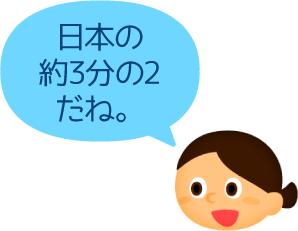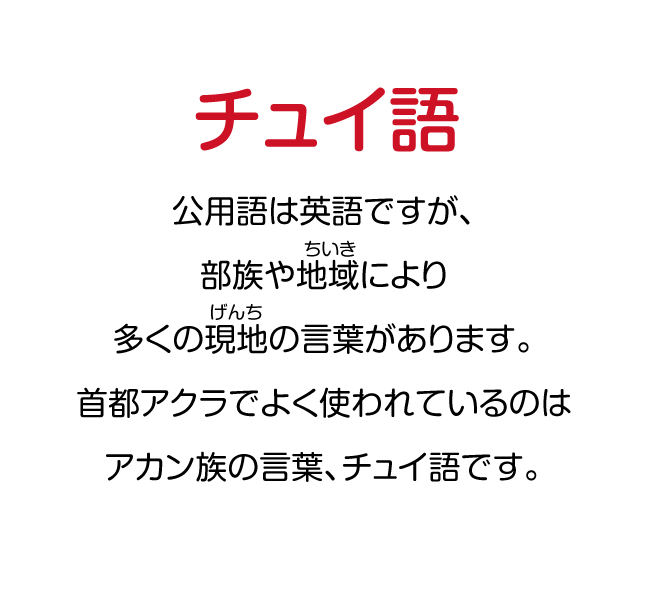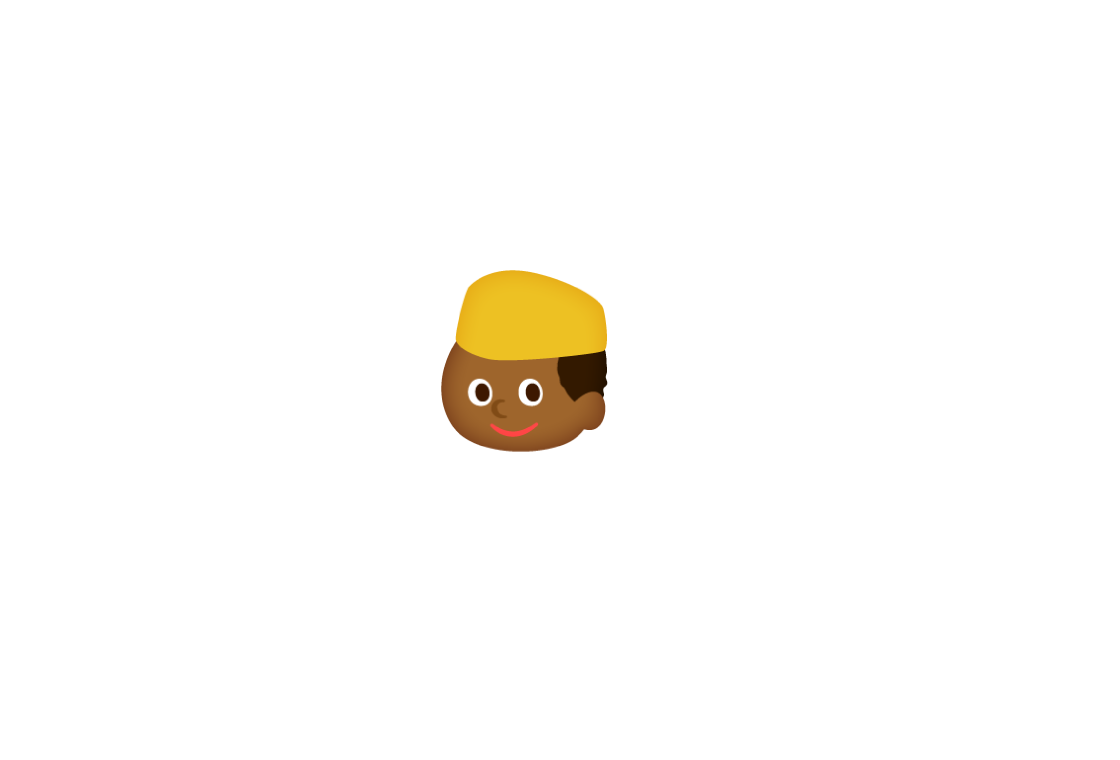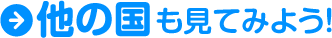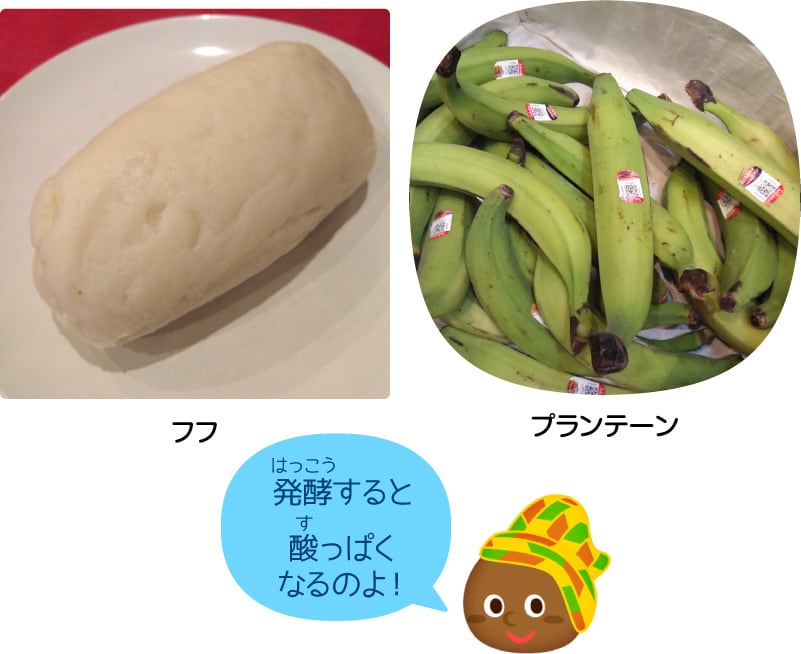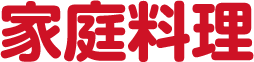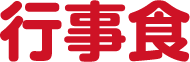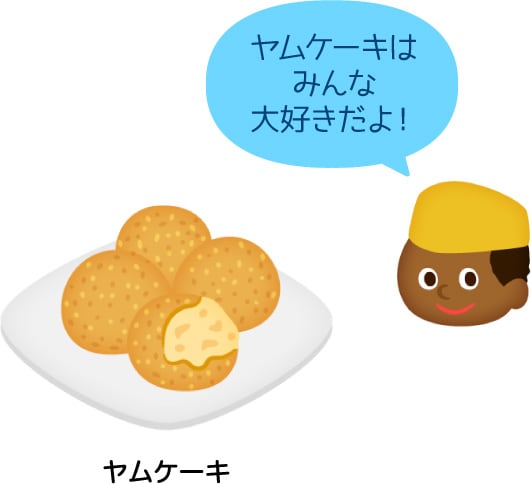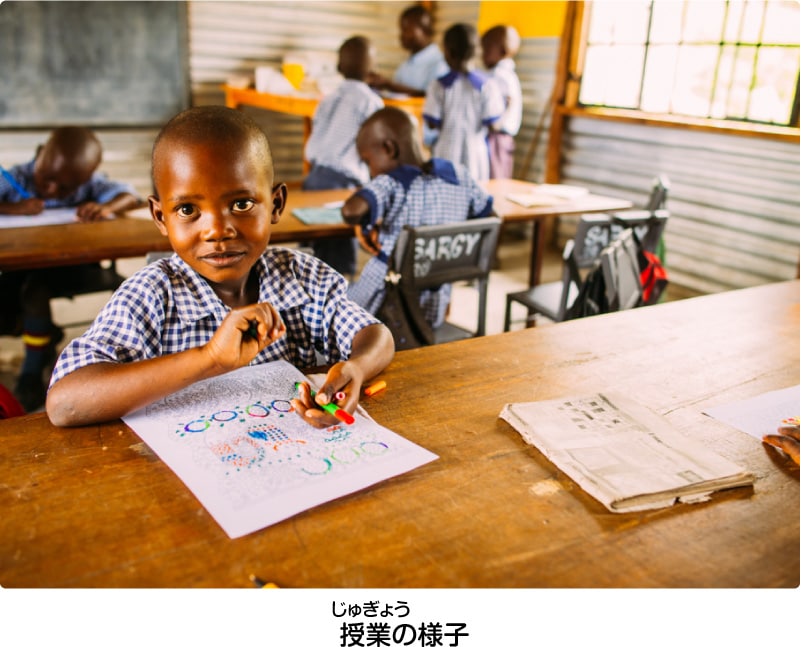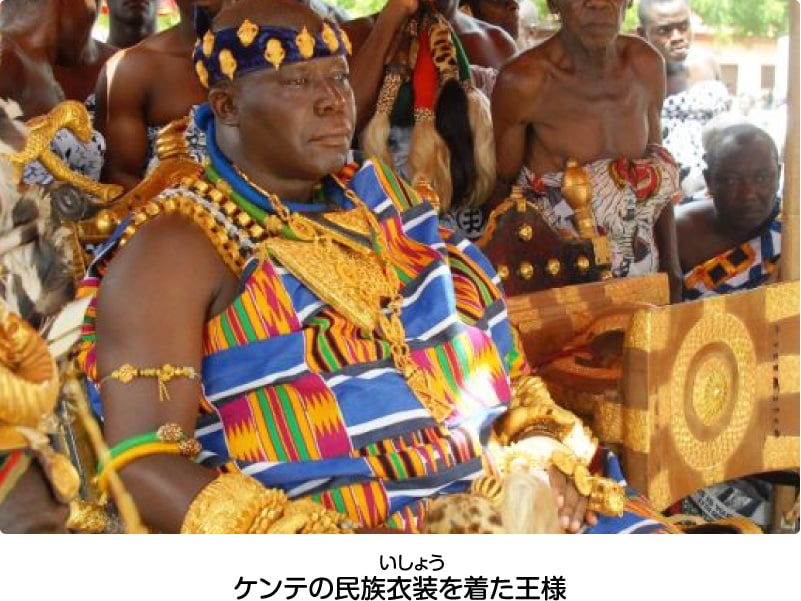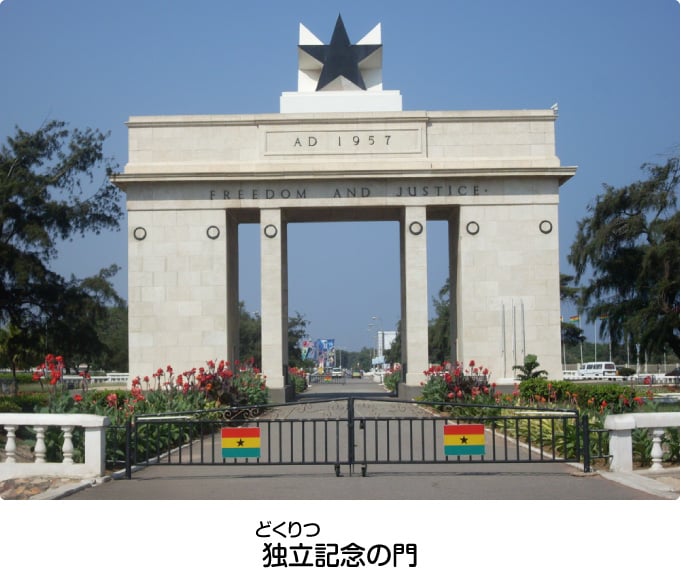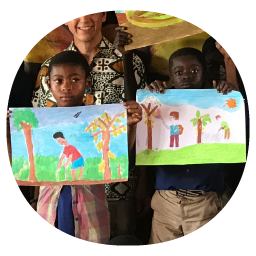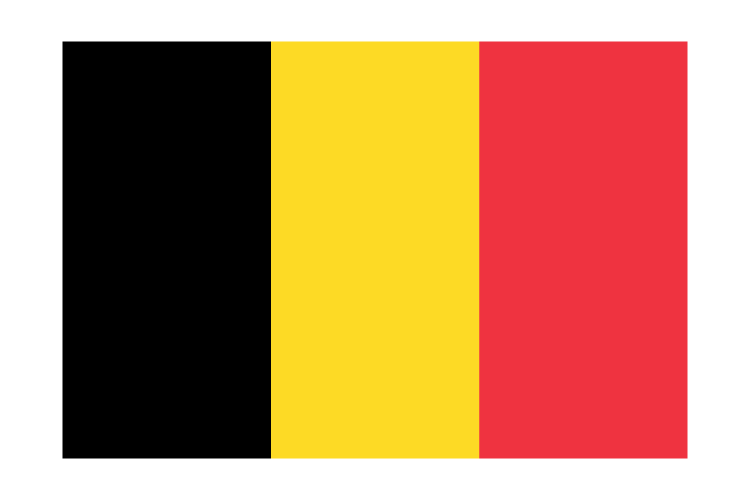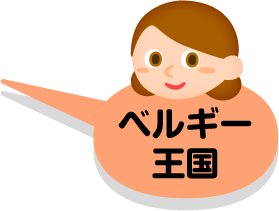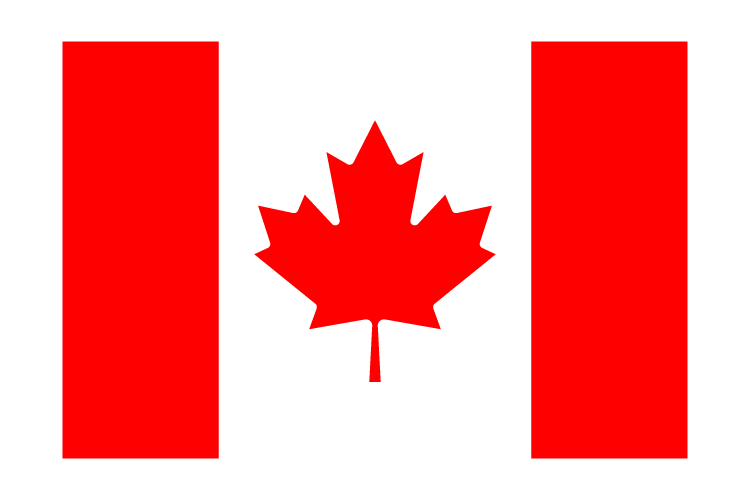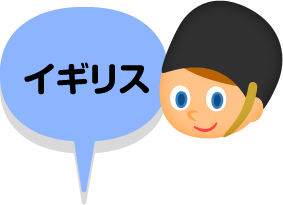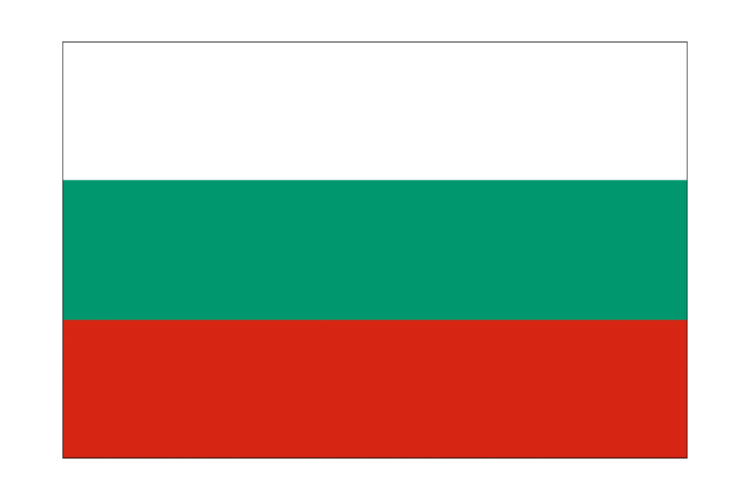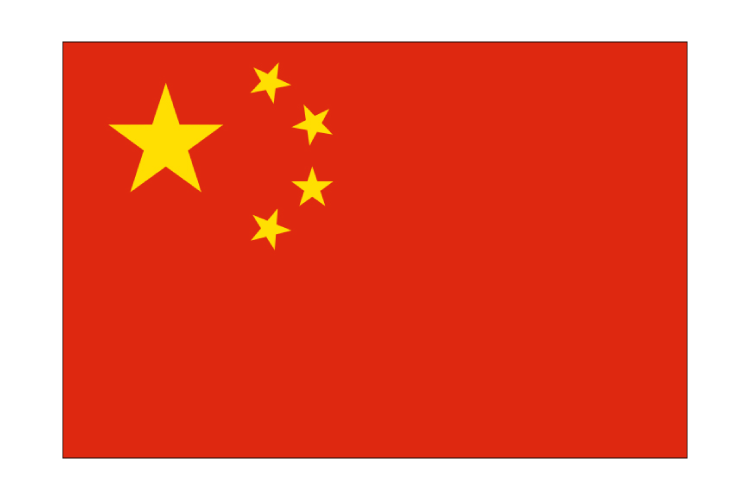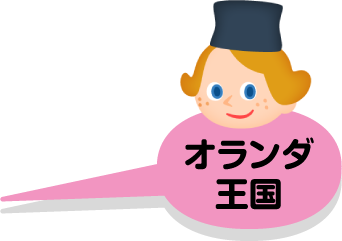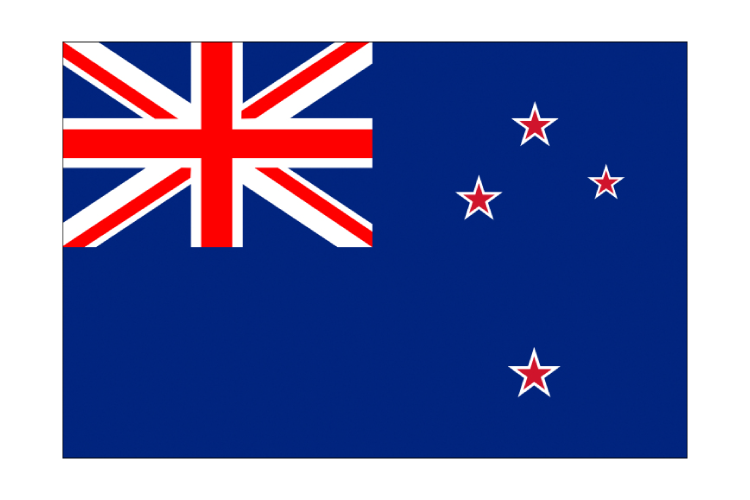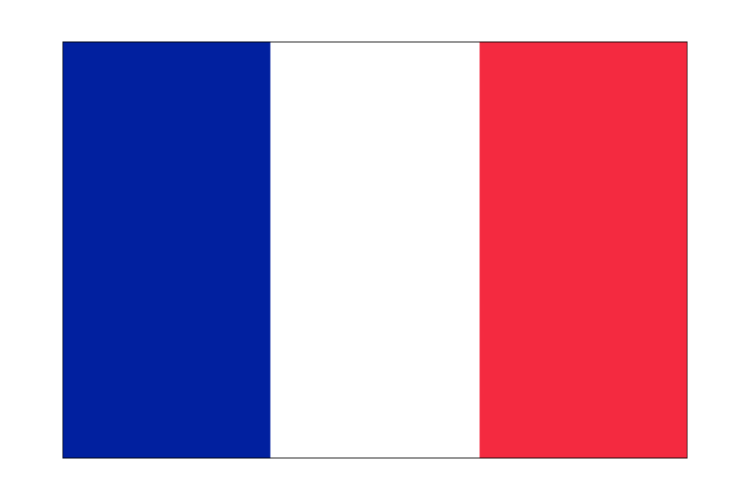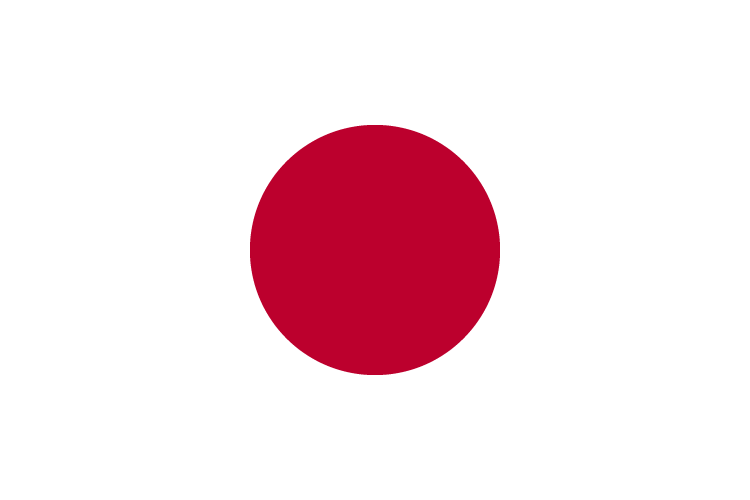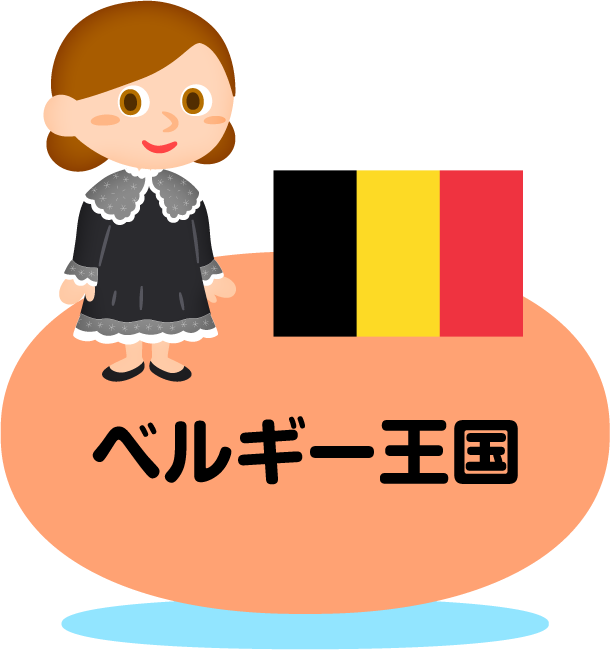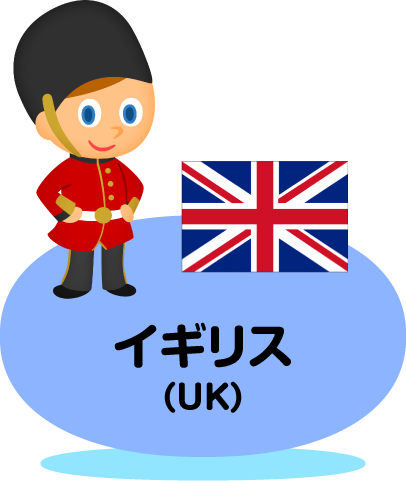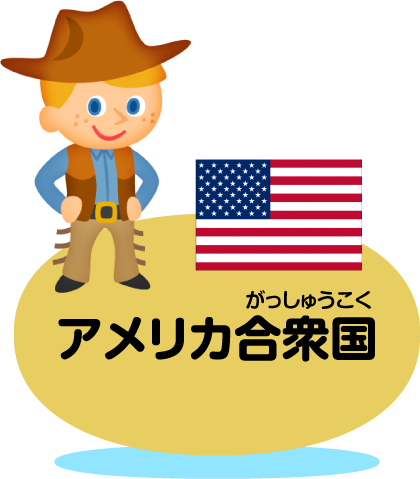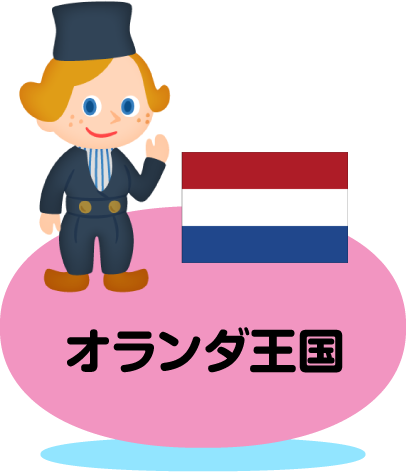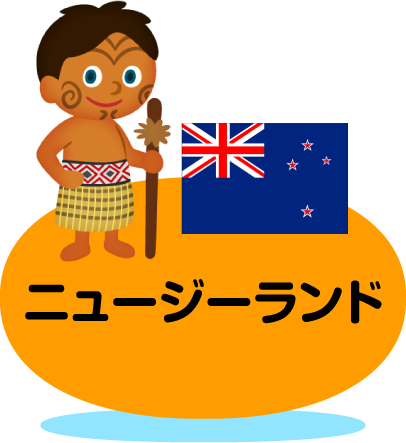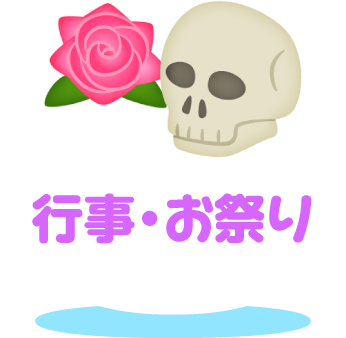ガーナはチョコレートの原料になるカカオの産地です。カカオ“豆”といいますが、実はカカオはフルーツなんです。ラグビーボールよりひと回りほど小さい実の中に30〜50つぶのカカオ豆が入っています。ガーナは、世界第2位のカカオ生産国です。日本もガーナからたくさんのカカオを輸入していますよ。
ガーナ国内ではカカオをいろいろな加工品にしています。パンやビスケットにしたり、ドリンクにしたり、お酒にしたり。石けんやスキンクリームにもなるんです。さすが、世界で2位の生産量をほこるガーナのカカオ、日々の生活にカカオがとけこんでいるんですね。