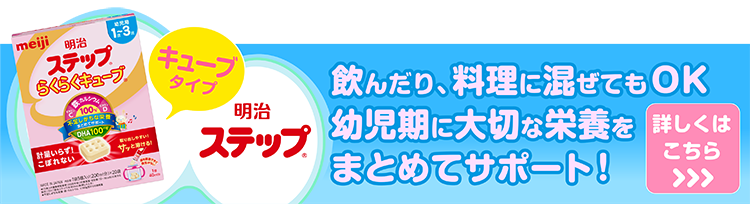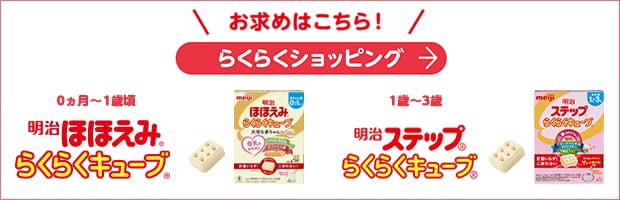【医師監修】母乳はいつまであげる?タイミングの目安と注意点について

母乳をいつまで続けるか悩んでいませんか?この記事では、卒乳の平均時期や卒乳のサイン、注意点をご紹介します。
この記事の監修者
-
- 氏名:野田慶太
- 経歴:保有資格 医師・小児科専門医
- 小児科医として子どもの病気の診療に当たるだけでなく、救急医として子どものケガの診療にも当たっている。また、5人の子どもの父でもあり、現在も育児に当たっている。
母乳はいつまであげる?
母乳育児をいつまで続けるか、決まった答えがあるわけではありません。国や文化でも異なりますし、赤ちゃんの成長のペースやお母さんの健康状態によっても変わります。
この記事では日本での一般的な状況と、国際的な推奨をご紹介しますが、あくまで目安と考えてください。
日本での平均は生後1歳半
厚生労働省の資料によると、日本では1歳から1歳半頃までに卒乳する割合が最も多いです。また、別の調査では、1歳時には約半数、1歳半では約20%の赤ちゃんが母乳を続けているというデータがあります。
1歳〜1歳半の時期は、離乳食が3回食になり、食べ物から多くの栄養を摂取できるようになり、そしてお子さんの身体的な発達や社会性の発達が進む時期と重なります。また、保育園への入園やお母さんの職場復帰などの生活環境の変化も、卒乳のきっかけになることが多いでしょう。
しかし、これはあくまで平均であり、個人差が大きいことを忘れてはいけません。「うちの子は平均より長い/短いから大丈夫かな?」と心配する必要はまったくありません。お子さんの成長ペースや生活の状況に合わせて、柔軟に考えていくことが大切です。
WHOの推奨は2歳以上まで
WHO(世界保健機関)はより長期的な母乳育児の推奨をしています。生後6ヵ月までは母乳のみで育てる完全母乳を推奨し、そのあとは補完食(離乳食)を開始しつつ、2歳あるいはそれ以降まで母乳育児を続けることを推奨しています。
これは、特に発展途上国などにおいて、母乳が感染症から赤ちゃんを守る重要な役割を果たすことや、栄養状態を維持するうえで欠かせないものであるという背景があります。
母乳は、お子さんの成長に必要な栄養素を供給するだけでなく、免疫物質や成長因子なども含まれており、2歳以降もそのメリットは失われないと考えられています。
もちろん、WHOの推奨は世界的な視点からのものであり、日本の生活環境や医療体制が整っている状況とは異なる部分もあります。この推奨を「母乳にはそれだけの価値がある」という理解として受け止めていただければと思います。大切なのは、お子さんの健康と成長をふまえ、ご家庭の状況に合わせえて最良の選択をすることです。
母乳育児の3つのメリット
母乳育児を続ける期間について悩むかもしれませんが、母乳が赤ちゃんにもお母さんにもメリットがあることは間違いありません。ここでは、母乳の3つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
赤ちゃんが栄養素や免疫物質を得られる
母乳は赤ちゃんにとって理想的な栄養源です。
母乳の成分は、赤ちゃんの成長段階に合わせて日々変化します。新生児期には初乳として免疫物質が凝縮されたものが分泌され、そのあとも、赤ちゃんの脳や体の発達に必要なタンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルなどが最適なバランスで含まれています。また、消化吸収されやすくなっており、赤ちゃんの未熟な消化器官でも負担になりにくいのが特徴です。
また、母乳には、お母さんから赤ちゃんへ受け継がれる免疫グロブリン(IgAなど)や、体内への細菌の侵入を防ぐ細胞(白血球)、善玉菌を育てるオリゴ糖などが豊富に含まれています。
これらは、赤ちゃんの免疫システムが未熟な期間、病原菌やウイルスから体を守る強力な免疫力として機能します。風邪や中耳炎、尿路感染症などの感染症にかかるリスクを低減し、もし病気にかかっても重症化しにくくする効果が期待できます。
加えて、母乳に含まれるDHA(ドコサヘキサエン酸)などの脂肪酸は赤ちゃんの脳や神経系の発達に不可欠な成分です。
関連記事:ほほえみクラブ 母乳は赤ちゃんにとって、栄養学的にも最良です。
ママの産後の回復を早められる
母乳育児は、赤ちゃんだけでなく、出産後のお母さんの体にもよい影響をもたらします。
赤ちゃんが母乳を吸うと、お母さんの体内ではオキシトシンというホルモンが分泌されます。このオキシトシンは、愛情ホルモンとも呼ばれる一方で、子宮を収縮させる作用があります。出産後に子宮が元の大きさに戻るのを助け、悪露(おろ ※出産後の出血)を減らす効果が期待できます。これにより、産後の回復が早まり、貧血のリスクも低減されます。
母乳を作る過程で、お母さんの体は多くのエネルギーを消費します。授乳中は1日に約500kcal消費すると言われており、これは軽い運動に匹敵するカロリー消費量です。
そのため、産後の体重を自然に戻しやすくなる効果も期待できます。ただし、過度なダイエットは禁物です。お母さん自身の栄養も大切にし、バランスの取れた食事を心がけましょう。
長期的な視点で見ると、母乳育児はお母さんの健康にも寄与します。乳がんや卵巣がんのリスクを低減させたり、骨粗しょう症や2型糖尿病の発症リスクを低下させたりする可能性が示唆されています。
スキンシップによって幸福感が生まれる
母乳育児は、赤ちゃんへの栄養補給の手段というだけではありません。お母さんと赤ちゃんとの間に深い絆を育み、精神的な安定をもたらします。
授乳中、お母さんと赤ちゃんはぴったりと肌を寄せ合い、アイコンタクトを取るなど、濃密なスキンシップをします。この触れ合いは、赤ちゃんの心に安心感を与え、お母さんの母性も強くします。
授乳によって分泌されるオキシトシンは、お母さんの心を落ち着かせ、リラックスさせる効果があります。母性を育むホルモンとも言われ、幸福感や満足感、赤ちゃんへの愛情を深めることにつながります。
産後のホルモンバランスの変化によって不安定になりがちなお母さんの精神的なサポートをし、育児への前向きな気持ちを育む手助けとなります。
赤ちゃんも、お母さんの抱っこや優しい声、匂いを感じながら授乳することで、安心感を得て情緒が安定します。このような安心できる環境は、赤ちゃんの心身の健やかな発達にもよい影響を与えます。
このように、母乳育児は赤ちゃんに栄養と免疫を与えるだけでなく、お母さんの体と心の回復を助け、親子の絆を深めるという、大きなメリットがあるのです。
卒乳タイミングの目安
母乳育児には多くのメリットがありますが、いつかは卒乳の時期がやってきます。月齢などを気にしすぎず、赤ちゃんとお母さんの準備が整ったタイミングで進めることが大切です。ここでは、卒乳を考えるいくつかの目安をご紹介します。
1日3回の離乳食に慣れたとき
卒乳を考えるうえで重要な目安の一つとなるのが、離乳食の進み具合です。生後6ヵ月頃から離乳食を始め、1歳頃には3回食に移行するのが一般的です。
離乳食が順調に進み、形のあるものを噛みつぶせるようになり、母乳以外の食べ物で赤ちゃんが必要な栄養を十分に摂取できるようになれば、母乳は主要な栄養源としての役割を終え、精神的な安心感や水分補給の役割が大きくなります。
離乳食をしっかり食べるようになると、赤ちゃん自身が母乳を飲む量が減ったり、欲しがる回数が減ったりすることがあります。また、食事中に母乳を欲しがらなくなるのもサインの一つです。
職場復帰や入園が決まったとき
職場への復帰やお子さんの入園などライフスタイルの変化も、卒乳を考える大きなきっかけとなります。
育児休業を終えて職場復帰が決まった場合や、お子さんが保育園・幼稚園に入園する場合など、お母さんの生活リズムが大きく変わることがあります。授乳の時間が限られたり、日中に離れて過ごす時間が増えたりすることで、自然と授乳回数が減り、卒乳へとつながることが多いです。
このようなライフイベントが決まっている場合は、復帰や入園の数ヵ月前から計画的に卒乳の準備を進めることができます。例えば、少しずつ授乳回数を減らしたり、昼間の授乳を減らしたりするなど、段階的に進めることで、赤ちゃんとお母さん双方への負担を軽減することができます。
次の子どもができたとき
二人目、三人目のお子さんを意識したり妊娠したりした場合も、卒乳を考えるタイミングになることがあります。
妊娠すると、ホルモンバランスの変化により母乳の分泌量が減ったり、味が変わったりすることがあります。また、妊娠中の体で授乳を続けることは、お母さんにとって体力的な負担が大きくなることもあります。無理なく次の赤ちゃんを迎えるためにも、卒乳を検討するよい機会となります。
ただ、お母さんの体調が悪くなく負担も大きくなければ、タンデム授乳(妊娠中も授乳を続け、出産後も上の子と下の子に同時、あるいは交互に授乳すること)を選択する方もいらっしゃいます。
これらの目安はあくまで参考です。一番大切なのは、お子さんの様子やお母さんの気持ち、そしてご家族の状況を総合的に考慮して、最適なタイミングを見つけることです。
卒乳については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
卒乳時の注意点
卒乳は、赤ちゃんの成長の証であると同時に、お母さんにとっても大きな節目です。スムーズに進めるためにはいくつかの注意点があります。
授乳回数は徐々に減らす
授乳は段階的に減らしていくことをおすすめします。
例えば、昼間の遊びに夢中なときや離乳食後など、赤ちゃんの執着が少ない授乳から減らし、抱っこや絵本の読み聞かせなどのスキンシップで気持ちを別のことに向けましょう。授乳間隔を少しずつ空け、一般的に最も執着の強い夜間授乳を最後にやめるのがスムーズです。授乳回数を減らす分、水分補給(水やお茶など)をこまめにおこなうことも大切です。
ただし、急な卒乳は赤ちゃんとお母さん双方に負担をかける可能性があります。急に母乳がもらえなくなると、赤ちゃんは不安を感じ、情緒不安定や夜泣きが増えることがあります。
また、急に授乳をやめると母乳が溜まり、乳腺炎(乳房の炎症)を引き起こすリスクが高くなります。乳腺炎になると乳房の痛み、腫れ、熱感、発熱などの症状が現れ、ひどい場合は医療機関での治療が必要になるので、気を付けましょう。
搾乳して乳腺炎を予防する
卒乳の過程でおっぱいが張って痛みを感じることがあります。これは母乳が作られ続けているため、おっぱいのなかに母乳が溜まってしまい、乳腺炎(乳房の炎症)を引き起こしている場合があるからです。そこで乳腺炎を予防するために適切に対処する必要があります。
まずは、最後の授乳から1〜3日経って痛くなりそうと感じたら搾乳するといいでしょう。
乳房が張って熱感がある場合は、冷やしたタオルなどで冷やすと痛みが和らぎます。また、無理をせず、体を休めることも大切です。
もし、乳房の強い痛み、赤み、熱感、しこり、そして発熱(38.5度以上)などの症状が出た場合は、助産師、またはかかりつけの産婦人科医に相談して適切な治療を受けてください。
卒乳は、赤ちゃんとお母さんの双方にとって身体的にも精神的にも大きな変化をともないます。焦らず段階的に進めること、そして何よりもお母さんが一人で抱え込まないことが大切です。パートナーや家族、地域の助産師や保健師、産婦人科医や小児科医など、周囲のサポートを積極的に活用してください。
赤ちゃんとママの状況に合わせて母乳育児をしよう
母乳は赤ちゃんにとって最良の栄養であり、母乳育児はお母さんにとっても素晴らしい経験となる一方で、さまざまな課題や悩みも伴います。しかし、母乳育児の期間や卒乳のタイミングにこうあるべきという決まったルールはありません。
赤ちゃんの食欲、成長のペース、母乳への執着は赤ちゃん一人一人それぞれ異なります。
また、産後の回復状況、体質、精神的なゆとり、仕事や生活環境の変化など、お母さんの環境や状況も十人十色です。
大切なのは、誰かの基準に合わせるのではなく、お子さん一人ひとりの発達と、お母さんの体調や気持ち、そしてご家庭の状況を総合的に見て、最適な選択をすることです。
無理をしてストレスを抱えながら母乳育児を続けるよりも、お母さんや家族が心穏やかに、笑顔で育児できることのほうが赤ちゃんにとっても大切です。もし母乳育児がうまくいかないと感じたら、混合栄養やミルク育児を選ぶことも問題ありません。ミルク育児であっても赤ちゃんへの愛情は変わらず、十分に愛情を育むことができます。
明治では「明治ステップ」というフォローアップミルクをご用意しております。
フォローアップミルクとは、離乳食が始まった赤ちゃんの栄養を補うために作られたミルクで、乳幼児期に必要な鉄分やカルシウムなどが多く含まれているのが特徴です。母乳や育児用ミルクとは異なり、毎日の食事だけでは不足しがちな栄養をミルクで補うことが可能です。
母乳期間は、赤ちゃんの様子やママの体調・生活スタイルに合わせて育児用ミルクをうまく併用することで、無理なく授乳を続けることができます。
また卒乳のタイミングには、離乳食だけでは不足しがちな栄養を補うために、フォローアップミルクを積極的に取り入れていきましょう。赤ちゃんの成長に必要な鉄分やカルシウムなどをしっかりサポートできるので、食事との組み合わせで栄養バランスを整える心強い味方になります。
授乳期間中は、悩んだり迷ったりすることもたくさんあるでしょう。そんなときは、一人で抱え込まずに、小児科医、助産師、保健師、あるいは信頼できるご家族や友人など、周囲の人に相談してみてください。お子さんの成長を温かく見守りながら、お母さんと赤ちゃんにとってベストな形で母乳育児の期間を過ごし、そして笑顔で次のステップへと進んでいけるよう、心から応援しています。