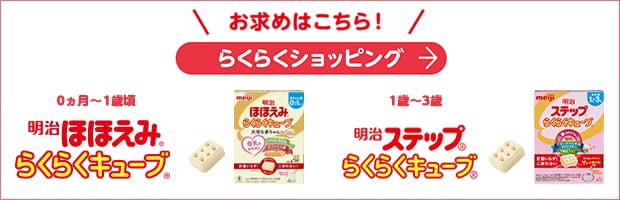【医師監修】新生児が寝ない理由とは?寝かしつけるコツや対策について

新生児の赤ちゃんがなかなか寝てくれず困っている方も多いでしょう。新生児は生活リズムが整っておらず、さまざまな理由で寝つけなかったりする場合があります。この記事では新生児の赤ちゃんが寝ない理由や寝かしつけるコツ・対策について解説します。
この記事の監修者
-
- 氏名:井上信明
- 経歴:小児科専門医・指導医。日本、アメリカ、オーストラリアにて診療。科学的根拠に基づく医療の提供を通じ、こどもたちとそのご家族に、安全と安心を届けることを意識して執筆に従事。
新生児が寝ないケース
まず新生児が寝ない状況には、どのようなものがあるのか、具体的なケースについてご紹介いたします。
泣いてばかりで寝ない
新生児の赤ちゃんは、さまざまな理由で泣き続けるために、なかなか寝つけないケースがあります。
新生児の赤ちゃんが泣く理由には、お腹が空いている、おむつが濡れていて不快である、不安を感じていて抱っこしてほしい、部屋の温度が暑すぎる、あるいは寒すぎる、痛みやかゆみを感じているなどがあります。もしなかなか泣き止まないようであれば、授乳やおむつ交換のタイミングではないか、室温が適切かなど、赤ちゃんが泣き止まない理由がないか、確認するとよいでしょう。
なお、いろいろと確認し、可能性のある原因を解決するように対応してみても泣き止まない場合、病気が隠れている可能性もありますので、医療機関を受診することをおすすめします。
眠りについてもすぐに起きる
新生児の赤ちゃんが、眠ってもすぐに起きてしまうケースもあります。
新生児期の赤ちゃんは、通常1日の3分の2ほどの時間を睡眠に費やしていますが、2~3時間ほどの睡眠と1~1.5時間の覚醒を繰り返します。睡眠中は、レム睡眠と呼ばれる浅い眠りと、ノンレム睡眠と呼ばれる深い眠りを繰り返していますが、レム睡眠の割合が多めです。そのためにちょっとした刺激で目が覚め、なかなか深い眠りに入っていけないことがあります。
なお生まれたときの体重が2,500g未満である低出生体重児では、睡眠時間が短くなる傾向があります。
ミルクをあげても寝ない
お腹が空いているはずなのに、しっかりとミルクをあげても寝ないケースがあります。
この場合、赤ちゃんがお腹いっぱいになるまでミルクを飲むことが影響している可能性があります。その理由の一つとして、赤ちゃんは胃のなかにたくさんミルクが入っていると、簡単に食道にミルクが逆流することがあり、そのために胸焼けがして不快に感じてしまい、なかなか眠ることができなくなってしまうことが挙げられます。
抱っこしていないと寝てくれない
抱っこしていないとなかなか寝てくれないケースもあります。
生まれる前の赤ちゃんは、母親のお腹のなかで、手足を曲げてまるで抱きしめられるような体勢になっていました。新生児の赤ちゃんにとっては、少し前までずっとそのような体勢でいたため、生まれたあとも抱きしめられると安心感を覚えると考えられています。眠くなったとき、しっかりと抱きしめられていることで深い眠りに入ることができます。しかし、不安を感じていて、まだ浅い眠りの状態でベッドに移されると、すぐに目が覚めてしまうことがあります。
新生児が寝ない理由とは?
それでは新生児はどのような理由で寝ないのでしょうか?新生児が寝ない具体的な理由について、その代表的なものをご説明します。
すぐにお腹が空いてしまう
新生児の赤ちゃんでは、すぐにお腹が空いてしまうことが、眠れない理由となりえます。
新生児の赤ちゃんは、胃の大きさがまだ小さいため、一回に飲むことができるミルクの量が限られています。そのため、ミルクを飲んでもしばらくするとお腹が空いてきます。お腹が空いてきたタイミングで眠くなると、なかなか寝つけなくなってしまいます。
モロー反射
新生児の赤ちゃんでは、モロー反射が眠れない理由となることがあります。
モロー反射は原始反射と呼ばれる生まれた直後からみられる反射で、突然光や音の刺激が加わると、その反応して両腕を左右に大きく開き、そのまま手を広げた姿勢を一瞬保ったのち、ゆっくりと抱きつくような形で両腕を胸のほうに引き寄せます。この動きを見ることで、赤ちゃんに神経系の異常がないか確認することができますが、生後2〜4週間あたりが最も顕著にみられます。
モロー反射は文字通り反射であり、刺激に対する正常な反応なので止めることができません。赤ちゃんによっては刺激にとても敏感で、部屋の扉を閉める音のようなちょっとした生活音にも反応してモロー反射が起こることがあります。そのような場合は、反射の動きが影響して、なかなか寝つけなくなってしまいます。
体調不良
赤ちゃんの体調が悪いと、なかなか眠れなくなってしまうことがあります。
新生児の赤ちゃんでは、痛みやかゆみがあっても、症状を訴えたり、その場所に自分の手を当てたりすることができません。そのため、少し体調が悪いだけでも寝られないという症状で訴えることがあるのです。その他にも、鼻詰まりや咳がひどくなることも、寝つけない理由になります。
なお新生児の赤ちゃんに熱が出る、大量に吐く、ぐったりしている、皮膚の炎症の範囲が広がってきた、へそやふともものつけ根のヘルニアが飛び出して戻らないなどの症状がみられる場合、緊急性の高い病気の可能性があります。この時期の赤ちゃんには、病気と戦う力も十分に備わっていないため、早めに医療機関を受診することを強くおすすめします。
睡眠環境が整っていない
赤ちゃんにとって快適な睡眠環境が整っていないと、なかなか寝つけないことが起こりえます。
例えば部屋の温度が暑過ぎたり寒過ぎたりすると、眠りに入れないことがあります。周囲の音がうるさい、赤ちゃんの寝ている部屋の照明がまぶしいなどの環境も、寝つけない理由となります。新生児の赤ちゃんは、「暑い・寒い」「うるさい」「まぶしい」と自分でいえないので、周りの大人が気を付ける必要があるでしょう。
新生児を寝かしつけるコツ
それではここで、新生児の赤ちゃんを寝かしつけるコツについて、いくつかご紹介いたします。
部屋の環境を整える
新生児の赤ちゃんが眠ることができるように、環境を整えましょう。
まずお部屋の室温は、夏は25~28度、冬は20~23度くらいが適温だといわれています。特に夏は湿度が高くなりやすいので、エアコンのドライ機能も使ってみましょう。逆に冬は部屋が乾燥してしまいます。湿度は年間を通して50~60%あたりが最適とされていますので、湿度が40%以下になってしまうときは、適宜加湿器を併用するとよいでしょう。また、エアコンの風が赤ちゃんに直接あたらないようにすることや、暖房器具を赤ちゃんから離れた場所に設置することも大切です。
その他にも赤ちゃんの寝る部屋にはテレビを置かず、赤ちゃんが寝ている間は、大人は別の部屋で会話をすることで、音による刺激を最小限にすることができます。またベッドは窓から離れた場所におき、遮光カーテンを使用し、寝ている間は極力照明を暗くすることで、光の刺激も避けることができるでしょう。
赤ちゃんが不快に感じる要素を取り除く
赤ちゃんが眠れるようにするためには、赤ちゃんが不快に感じる可能性のあるものを取り除いてあげることも有用です。
例えば着衣のタグが肌に触れて痛かったり、授乳後のゲップをうまく出せないなど、赤ちゃんは大人では気付きにくいさまざまな理由で不快に感じることがあります。その原因を探すことは容易ではないかもしれませんが、部屋の環境を整えるほかに、衣服の状態の確認したり、授乳後にはしっかりゲップをさせるなど、考えられる原因を一つずつ取り除いてあげてください。
生活リズムを整える
赤ちゃんの生活リズムを徐々に整えていくことも、有効な方法です。
朝起きて夜眠るという赤ちゃんの生活リズムは、一般的に生まれてから3〜4ヵ月の間で確立されていきます。このリズムは突然できるわけではなく、生まれる前から徐々に時間をかけて確立されます。
そのため、少しずつで構いませんので、しっかりと昼夜のリズムが整うように意識してみてください。例えば朝は部屋のカーテンを開け、しっかりと光を入れる、沐浴する時間を少しずつ夜の時間にシフトするなどです。
新生児の頃は、赤ちゃんだけでなく赤ちゃんのケアをするご家族の皆さんも生活のリズムを整えていく必要のある時期です。赤ちゃんが産まれるまでは大人主体であった生活が、赤ちゃん中心の生活に変化します。最初は慣れないかもしれませんが、少しずつ赤ちゃんの状態に合わせながら、昼と夜を区別する生活リズムを整えていきましょう。
夜の授乳は部屋の明るさを下げる
夜に授乳するときには、部屋の明るさを下げることで赤ちゃんを眠りにつかせやすくなります。
新生児期は、まだ2〜3時間おきに授乳しますので、どうしても夜中にミルクを欲しがります。そのときに部屋が明るすぎると、授乳後に眠りに戻りにくくなってしまいます。
そのため、赤ちゃんの寝る部屋は落ち着いた暖色系のテーブルランプを用意するなどして、部屋の照明を消しても落ち着いて授乳できるようにしておくとよいでしょう。可能であれば遮光カーテンを用意し、室内を昼は明るく、そして夕方以降は暗くできるようにしておきましょう。
おくるみを使う
おくるみを使って赤ちゃんを包んであげることも、赤ちゃんを寝つけやすくする方法です。
生まれる前の赤ちゃんは、母親のお腹のなかで、抱きしめられるような体勢になっていました。そのため、抱きしめられるような姿勢は赤ちゃんに安心感を与えます。あまり強く包み込むことは避ける必要がありますが、赤ちゃんをおくるみで包んであげて適度な圧迫感を与えることは、入眠を助けてくれるでしょう。
胎内音を流す
赤ちゃんが、産まれる前に胎内で聞いていた音と同じような音を聞かせてあげることも効果的です。
おくるみで包んであげることと同じように、新生児の赤ちゃんにとって、産まれる前の環境に近い環境は安心感を与えてくれます。そのため、胎内で赤ちゃんが聞いていたものと似た音を聴かせてあげることは、寝つきをよくすることにつながります。具体的には、テレビの放映時間外にみられる砂嵐状の映像できこえる音で、さまざまな周波数の音が同じ強さで混ざったホワイトノイズとも呼ばれる音です。実際は、動画共有サイトなどインターネット上に音源がありますので、試してみるとよいでしょう。
その他にも、胎内環境で聞こえる音を再現した音源もインターネット上にありますので、いろいろと試してみてください。
スキンシップを普段よりも多くとる
意識して赤ちゃんの肌に触れ、スキンシップを多くとることも試してみましょう。
赤ちゃんが不快に感じる原因を取り除き、いろいろと赤ちゃんを寝つけやすくする方法を試してみてもいまひとつ効果を感じられないときは、赤ちゃんが不安を感じているのかもしれません。そのようなときは、スキンシップをとり、赤ちゃんの肌に直接触れることを試してみてください。例えば、子守唄を歌いながら、赤ちゃんの肌を直接さすってあげることでスキンシップを増やすことができます。あまり強い刺激にはならないように、優しく触れてあげてください。
その他にも、赤ちゃんを寝かしつけるアイディアについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
関連記事:ほほえみクラブ 寝かしつけのアイディア
新生児が寝つかなくても長時間目を離すのは注意!
赤ちゃんがなかなか眠ってくれないと、ついその場を離れたくなってしまう事もあるかと思います。特に赤ちゃんが寝ている間に済ませたい用事があると、赤ちゃんのことが気になりつつも、どうしても目を離してしまいがちです。
しかし、赤ちゃんをひとりだけにすることに対する危険性も知っておく必要があります。赤ちゃんを寝かせるために横にする場合は、平らで固いマットレスの上に寝かせます。また赤ちゃんの周囲には、ぬいぐるみやタオル、枕も置かないようにしましょう。まだ寝返りもうてない状態ですから、万が一顔をこれらのもので塞がれてしまうと、窒息の危険性があるからです。
どうしても目を離す必要があるときには、最小限の時間にするようにしましょう。
赤ちゃんが眠りやすい環境を整えて、正しい生活リズムを作ろう
夜間の授乳には「明治ほほえみ」がおすすめです。キューブタイプなら計量不要で入れるだけ、液体タイプなら哺乳瓶に注ぐだけで、簡単に授乳できます。母乳が足りないときや、育児をサポートする一つの手段として、ぜひお役立てください。