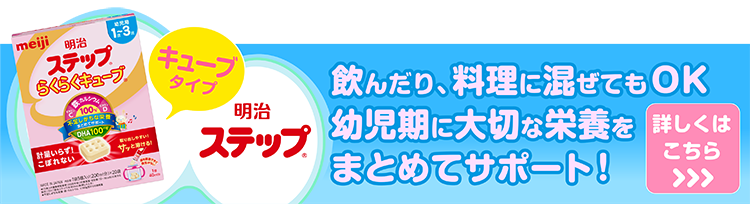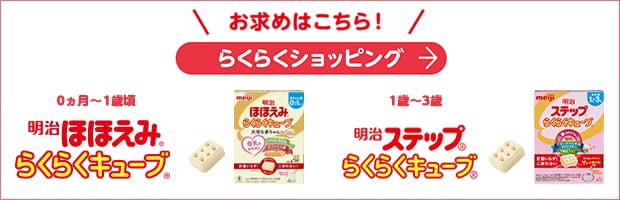【助産師監修】卒乳はいつから始める?時期と進め方のコツについて

「卒乳はいつから始めたらいいの?」という方に向けて、卒乳時期と進め方のコツをご紹介します。
この記事の監修者
-
- 氏名:金子芽依
- 経歴:保有資格 助産師
- 助産師として産科病棟・NICUで勤務したのち、現在は医療ライターとして活動中。妊娠・出産・育児に関する情報を、正確かつわかりやすく届ける。
卒乳とは
卒乳とは、赤ちゃんが自然と母乳を飲まなくなることをいいます。医学的に明確な定義があるわけではありませんが、赤ちゃんの成長にともなう大切な過程の一つです。
卒乳と断乳の違い
卒乳と断乳はどちらも授乳を終えることを指しますが、その意味や進め方には違いがあります。
卒乳は、赤ちゃんが自然と母乳を飲まなくなっていくことなので、赤ちゃん主体のやめ方です。離乳食が進み、食事から栄養がとれるようになると、赤ちゃん自身が少しずつおっぱいへの興味を失い、自然と卒業します。
一方で、断乳はママ主体の判断で進めるやめ方です。仕事への復帰、お薬の服用などの理由から「そろそろやめたほうがいいかな」と感じたときに、少しずつ授乳回数を減らしながら進めていきます。
卒乳の時期はどう決まる?
離乳食からエネルギーや栄養を取れるようになり、赤ちゃんが自然と母乳を飲まなくなったタイミングが、卒乳の時期です。卒乳の時期に正解はありません。
生後1歳6ヵ月頃までが目安
「厚生労働省の授乳・離乳の支援ガイド(2019年)」では、離乳の完了時期の目安を生後12〜18ヵ月頃としています。この頃になると、赤ちゃんは形のある食べ物をかみつぶせるようになり、食事からエネルギーや栄養をとれるようになってきます。
1日3回の食事に加えて、1〜2回のおやつを取り入れながら少しずつ母乳やミルクの回数が減っていきますが、離乳食の完了時期=卒乳ではありません。食事から栄養がとれるようになっていても、赤ちゃんがおっぱいを求めている場合は授乳が続くこともあります。
卒乳時期には個人差がある
1歳頃までに断乳するのが当たり前のようにいわれていた時期もありました。実際に、2002年以前の母子手帳には断乳の完了を書く欄があり、1歳を過ぎると断乳をすすめられるケースも多かったようです。
しかし、最近ではおっぱいの時間が、ママと赤ちゃんの絆を育てる大切な時間であることが明らかになり、授乳の終わり方や時期は「ママと赤ちゃんのペースで決めていい」という考え方が広がってきています。
母乳をあげる期間については、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
3つの卒乳方法
基本的に卒乳では、赤ちゃんが自然におっぱいを飲まなくなるのを待ちます。しかし、赤ちゃんのペースに合わせて、少しずつ卒乳へと進めていく方法もあります。
医学的に定まった卒乳方法があるわけではありませんが、次の3タイプに分けて考えるとわかりやすいでしょう。
自然卒乳
自然卒乳は、赤ちゃんが自然と母乳を飲まなくなるまで授乳を続ける方法です。ほかの卒乳方法に比べると、赤ちゃんの精神的な負担が少なく、ママのおっぱいトラブルも起こりにくい傾向があるといわれています。ただし、実際に自然卒乳できるケースは少なく、一時的な哺乳ストライキが多いとされています。
自然卒乳と哺乳ストライキの見極めのポイントとして、離乳食を食べられているかが重要な判断基準となります。
自然卒乳の場合は、赤ちゃんの機嫌も良く、離乳食やご飯をよく食べ、おっぱいを与えようとしなければ機嫌のよい傾向があります。
一方、哺乳ストライキの場合は、機嫌が悪く、離乳食もあまり食べず、コップで何かを飲むのも嫌がる傾向があります。
このような違いを目安に日々赤ちゃんを観察しながら、適切な対応を選択していきましょう。
計画的卒乳
計画的卒乳は、ママの都合に合わせて少しずつ卒乳へと進めていく方法です。ママが薬を飲む必要があるときや職場復帰の予定があるときなどにおこないます。
授乳を急にやめるのではなく、1週間に1回減らす、2〜3日に1回減らすといった形で、ゆっくり進めていきましょう。ママから授乳に誘うのは控えつつ、赤ちゃんが欲しがったときは無理に拒否せず、自然な形で回数を減らしていきます。
計画的卒乳では段階的に授乳の回数を減らしていくため、断乳するよりも赤ちゃんがストレスを感じにくく、ママのおっぱいトラブルのリスクも減らすことができます。
これまで授乳していた時間に、授乳以外のスキンシップを取るようにすると、ママも赤ちゃんも気持ちの面で安定しやすくなるのでおすすめです。
部分的卒乳
部分的卒乳は、母乳育児を完全にやめるのではなく、特定の時間帯だけ授乳をやめる方法です。この方法は、職場復帰などの生活スタイルの変化に対応しながら、母乳育児を継続したいママにとってよい選択肢の一つです。
職場復帰にともなう昼間の授乳停止では、保育園に預けている時間帯はミルクや離乳食で栄養を補い、朝の出勤前と帰宅後の夜間のみ授乳を継続します。これにより、仕事と母乳育児の両立が可能になります。
一方、睡眠確保のための夜間授乳停止は、夜間断乳とも呼ばれ、ママの体力回復や睡眠の質向上を目的として、夜間の授乳をやめる方法です。昼間は通常通り授乳を続けながら、夜間のみ授乳を控えることで、ママの負担軽減を図ります。
部分的卒乳は、ママと赤ちゃんの状況に合わせて柔軟に選択できる方法であり、完全な卒乳への準備段階としても活用できます。
卒乳のスムーズな進め方
少しずつ卒乳に進めていく場合は、ママと赤ちゃんに無理のないペースで進めることが大切です。ここでは、計画的卒乳のスムーズな進め方をご紹介します。
①卒乳日を決める
まずは卒乳する日を決めましょう。1〜2ヵ月ほどかけて取り組むスケジュールにすると、ママも赤ちゃんも気持ちに余裕を持って進めやすくなります。職場復帰のために卒乳を目指す場合は、復帰日よりも前に卒乳日を決めておくと安心です。
卒乳に向けて授乳の回数が減ると、赤ちゃんが夜に寝つけなかったり、ぐずってしまったりすることがあります。ママ自身も、おっぱいの張りがつらかったり、ホルモンバランスの変化によって気持ちが不安定になったりと、思った以上に大変に感じるかもしれません。
そのため、授乳を減らし始めるタイミングは、パパがお休みの日や家族のサポートを受けやすい日に合わせておくといいでしょう。
また、できればママや赤ちゃんが体調を崩しやすい真夏や真冬、季節の変わり目は避けておくのがおすすめです。
さらに、引越しや保育園の入園など、環境が大きく変わる時期も避けると安心です。赤ちゃんにとってストレスが少ないタイミングを選ぶことで、卒乳がよりスムーズに進みやすくなります。
②卒乳予定を赤ちゃんに伝える
卒乳をスムーズに進めるためには、赤ちゃんの心の準備も大切です。「おっぱいさんにありがとうしようね」「そろそろおっぱいとバイバイの準備をしようか」などと、やさしくシンプルな声かけが伝わりやすいでしょう。
言葉の意味がすべてわからなくても、ママの声のトーンや雰囲気から、赤ちゃんは少しずつ変化を感じ取ってくれます。卒乳をテーマにした絵本を読むのも、心の準備を進めるよいきっかけになります。
また、おっぱい以外の方法で安心して眠れるよう、次のような入眠時の新しい習慣を見つけておくのもおすすめです。
- 背中をトントンする
- お気に入りのぬいぐるみやタオルを抱かせる
- 絵本の読み聞かせをする
- 子守唄を歌ってあげる
こうした習慣を少しずつ生活に取り入れてみましょう。
③授乳回数を減らしていく
卒乳の日に向けて、授乳の回数をゆっくり減らしていきます。急に回数が減ると、ママはおっぱいが張って痛くなり、赤ちゃんは戸惑ってしまいます。
最初は1週間に1回だけ授乳を減らし、慣れてきたら2〜3日に1回減らすといったペースで、少しずつ回数を減らしていきましょう。ママと赤ちゃんにとって無理のないペースで進めることが大切です。
おっぱいを思い出して欲しがるときは、次のような工夫をしてみてください。
- お友だちと遊ぶ
- 外で元気に体を動かす
- お茶やお水を飲んで、気持ちを切り替える
赤ちゃんの気をそらすとストレスが減り、気持ちが落ち着きやすくなります。また、大好きなおっぱいを我慢している赤ちゃんの気持ちに配慮して、入浴のときにおっぱいが目に入らないようにしたり、搾乳する姿を見せたりしない工夫をすることも大切です。
授乳の回数を減らしていくと、喉が渇いたりお腹が空いたりしやすく、赤ちゃんがぐずりやすくなるかもしれません。離乳食を少し増やしたり、ミルクやお茶、水などでこまめに水分補給をしたりと、赤ちゃんの様子に合わせて対応してあげてください。
④卒乳時も赤ちゃんに声かけする
卒乳の日も、赤ちゃんに声かけをしてあげましょう。「今日でおっぱいはおしまいだよ」「いっぱい飲んでくれてありがとうね」など、スキンシップをしながら気持ちを伝えることで、赤ちゃんも気持ちの整理がつきやすくなります。
授乳は、赤ちゃんにとって安心できる大切な時間です。卒乳はそんなおっぱいとのお別れでもあり、赤ちゃんにとって大きな一歩です。
がんばった気持ちに寄り添い、前向きな声かけをしてあげましょう。「大きくなったね、すごいね」「これからもっとたくさんのおいしいものが食べられるよ」といった、がんばりを認める言葉や今後の楽しみを伝える言葉をかけて、赤ちゃんの新しいステップを応援してあげることが大切です。
また、卒乳後は、ママのおっぱいのケアがとても大切です。母乳の分泌はすぐに止まらないため、張ってつらいときは、少しだけ母乳を出して対処してください。
余裕のある卒乳スケジュールがおすすめ
卒乳を成功させるためには、余裕を持ったスケジュール作りが大切です。体調不良や予期せぬ事情が起きても対応できるよう、ゆとりを持ったスケジュールを立てておきましょう。
特に職場復帰の予定が決まっている場合は、復帰日よりも前に余裕を持って卒乳日を設定することで、万が一の延期にも対応できます。「この日までに絶対」と焦らず、お子さんとママのペースに合わせて柔軟に進めることが、スムーズな卒乳へとつながります。
また、体調がすぐれない時期や、引越しや入園などで生活環境が大きく変わる時期は控えたほうが無難です。ママと赤ちゃん、どちらもが落ち着いているタイミングを選んでみてください。授乳回数を減らしていくなかで、赤ちゃんの反応を細やかにチェックすることも大切にしましょう。
卒乳には明確な正解がないので、周りのペースを気にするよりも、赤ちゃんの成長に合わせて進めていくことが、結果的にうまくいくコツです。
卒乳は赤ちゃんのペースに合わせて進めよう
卒乳は、ママにとっても赤ちゃんにとっても大きな節目です。生活スタイルの変化に合わせて進める場合もあるかもしれませんが、できるだけママと赤ちゃんのペースを大切にするとスムーズに進みやすくなります。
卒乳のタイミングや方法に正解はないので、不安なときはまわりに頼ることも大切です。母乳育児をがんばってきたママ自身にも、優しい気持ちを向けてあげてください。
卒乳に向けて離乳食が進むなかで「ちゃんと栄養がとれているかな?」と心配になったときは、フォローアップミルクを取り入れるのも一つの方法です。
フォローアップミルクとは、離乳食が始まった赤ちゃんの栄養を補うために作られたミルクで、乳幼児期に必要な鉄分やカルシウムなどが多く含まれているのが特徴です。母乳や育児用ミルクとは異なり、毎日の食事だけでは不足しがちな栄養をミルクで補うことが可能です。
明治では、1歳頃からの成長をサポートするフォローアップミルク「明治ステップ」をご用意しています。赤ちゃんの栄養面が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。