とうもろこし
背の高い茎の中ほどに実をつけます。ひげは、めしべです。
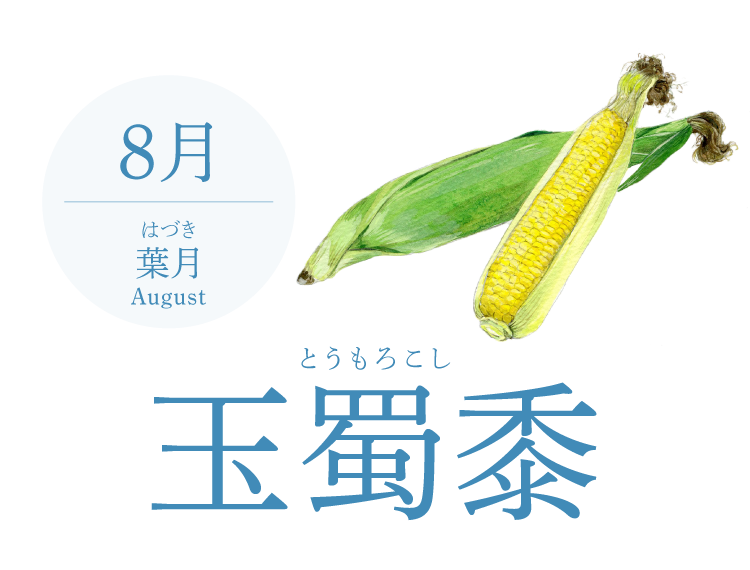
日本では夏の野菜としておなじみのとうもろこしは、世界の三大穀物の1つです。乾燥させた実は、世界中でさまざまな加工食品の原料や家畜の飼料(えさ)になっています。

とうもろこしは夏が旬。強い日差しを浴びて実が大きくなります。皮付きのとうもろこしの先にはひげがたくさんついていますが、このひげの数だけ実がついています。
とうもろこしにはいろいろな品種があります。日本では黄色や白の甘い実(スイートコーンという品種)を、ゆでたり焼いたりして食べるのが普通ですが、海外では実を乾燥させて使う品種のほうがたくさんあります。お菓子のポップコーンもその仲間で、爆裂種という品種です。

背の高い茎の中ほどに実をつけます。ひげは、めしべです。

皮の硬い爆裂種というとうもろこしの実を乾燥させ、加熱すると、中の水分が膨張して皮がポンとはじけます。

とうもろこしはお米と同じイネ科の植物で、エネルギー源になる栄養が詰まっています。原産地とされるメキシコなどでは、紀元前の大昔から乾燥させた実を粉にして主食として食べてきました。その種が15世紀末にコロンブスによってヨーロッパに伝わり、世界中に広まる中で、人が食べるほかに家畜の飼料などにも使われるようになりました。
今では、とうもろこしは小麦、米と並ぶ世界の三大穀物の1つです。アメリカや南米などで主に作られ、その6~7割は家畜の飼料に、残りは加工食品や工業製品などに使われています。アメリカでは燃料用の品種も作っています。日本は飼料用や加工食品用のとうもろこしをたくさん輸入しています。

とうもろこしは、さまざまな形で食べられています。
メキシコの人々が主食にするトルティーヤは、とうもろこしの粉を水で練り、薄くのばして焼いたパンです。これに肉や野菜を包んで食べる料理は、タコスといいます。とうもろこしの粉で作った生地をとうもろこしの皮で包んで蒸す、タマレスという料理もあります。日本でも、自家製のとうもろこしの粉をまんじゅうや団子にして食べる地域があります。
ほかに、パン、コーンフレーク、菓子など身近な食品にもとうもろこしの粉はよく使われています。また、とうもろこしの胚芽は、料理に使うコーン油の原料になります。
ひげは干すと漢方薬になります。食べ物ではありませんが、中南米や東ヨーロッパ、日本では、ひげや皮を使って人形を作る風習もあります。

メキシコでおなじみの主食。昔は家庭で手作りするのが当たり前でしたが、今では多くの店で売られています。手前はトルティーヤで具を包んだ料理タコス。

大昔からある、ちまきのような料理です。メキシコでは屋台で売られています。

とうもろこしの実をひいた粉などを原料にして作られています。

チェコやスロバキアに伝わる、とうもろこしの皮やひげで作られた愛らしい人形。

生のとうもろこしは、収穫した直後から甘みが減っていくので、なるべく新鮮なうちに加熱するのが一番です。ゆでたり蒸したりするほかに、電子レンジで加熱するのも手軽で甘みがより感じられます。皮をむいて(皮は3~4枚付けたままでも)1本ずつラップで包み、600Wで4分ほど加熱します。
加熱したとうもろこしは、バターで焼いてしょうゆをからめてもいい香りです。芯にもうま味があるので、実をこそげてスープにするときは、芯も包丁の背でこすって白い汁を押し出し、一緒に加えるとよりおいしくできます。


ひき肉だねにとうもろこしを混ぜてしゅうまいの皮に詰め、上にもとうもろこしをたっぷりのせて電子レンジで蒸します。