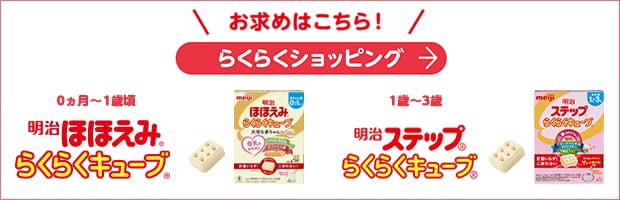【医師監修】新生児(赤ちゃん)にミルクをあげる間隔は?適切なミルクの量について

新生児(赤ちゃん)のミルクの間隔や量について悩んでいるお母さんも多いかと思います。今回は新生児にあげるミルクの間隔や量について紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
この記事の監修者
-
- 氏名:野田慶太
- 経歴:保有資格 医師・小児科専門医
- 小児科医として子どもの病気の診療に当たるだけでなく、救急医として子どものケガの診療にも当たっている。また、5人の子どもの父でもあり、現在も育児に当たっている。
ミルクの間隔は赤ちゃんの成長によって変わる
赤ちゃんは、生まれてからわずかな期間で驚くほど成長します。その成長に合わせて、ミルクを必要とする量や授乳の間隔も大きく変わっていきます。
生まれたばかりの新生児期は胃が小さく、一度にたくさんのミルクを飲むことができません。そのため、少量ずつ何度もミルクを欲しがります。この時期は赤ちゃんが欲しがる様子を見逃さず、欲しがるときに欲しがるだけあげることが基本となります。授乳間隔も短く、2〜3時間おきになることが一般的です。夜間も、赤ちゃんが欲しがれば授乳が必要です。
しかし、生後1ヵ月、2ヵ月と経つにつれて赤ちゃんの胃は少しずつ大きくなり、一度に飲めるミルクの量が増えていきます。それにともなって授乳間隔も徐々に長くなり、3〜4時間おきになるなど、少しずつ規則的なリズムができてきます。また、身体活動が増え、睡眠時間も変化するため、必要なエネルギー量も変わってきます。
このように、ミルクの量や間隔は、赤ちゃんの成長、体重増加、活動量、睡眠パターン、そして離乳食の進み具合など、さまざまな要因によって常に変化していくものです。商品に記載されていたり、本に書かれていたりするミルクの量の目安はあくまで一般的なものであり、赤ちゃん一人一人の様子をみて、その子に合ったペースでミルクをあげることが大切です。
【月齢別】ミルクの量と間隔
ここでは、一般的な赤ちゃんの成長段階に応じたミルクの量と間隔の目安をご紹介します。繰り返しになりますが、これはあくまで目安であり、赤ちゃんの個性や体調によって量や間隔は大きく異なることをご理解ください。心配な場合は、かかりつけの小児科医や助産師に相談しましょう。
参照:平成23年度 厚生労働科学研究費補助金 (成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)/「乳幼児身体発育評価マニュアル」
新生児
新生児のミルクの量は1回あたり20〜80ml程度から始め、徐々に増やしていきます。授乳間隔は2〜3時間おきが目安です。赤ちゃんにミルクを欲しがる様子(口をパクパクさせる、指を吸う、泣き出すなど)が見られたら、欲しがるだけ与えましょう。
この時期は、赤ちゃんの体重増加が重要です。1日あたり20〜30g程度の体重増加が目安となります。授乳回数は1日8〜10回以上になることも珍しくありません。夜間も授乳が必要な時期です。無理に間隔を空けようとせず、赤ちゃんの欲求に応えてあげましょう。
また以下の記事で赤ちゃんに必要なミルクの量についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:ほほえみクラブ 赤ちゃん(新生児)に必要なミルクの量を知ろう
生後1ヵ月~2ヵ月
生後1ヵ月〜2ヵ月の赤ちゃんのミルクの量は、1回あたり80〜160ml程度に増えていきます。授乳間隔も3〜4時間おきが目安となります。
この時期になると、胃の容量が大きくなり、一度に飲める量が増えるため授乳間隔が少しずつ開いてきます。ですが、赤ちゃんの飲む量には個人差が大きいため、赤ちゃんが満足しているか、体重が順調に増えているかを確認しながら調整しましょう。夜間の授乳回数が徐々に減ってくる赤ちゃんもいます
関連記事:ほほえみクラブ 生後1ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後2ヵ月
3ヵ月~4ヵ月
3ヵ月〜4ヵ月の赤ちゃんのミルクの量は、1回あたり160〜200ml程度が目安となり、授乳間隔も4時間おき程度に定まってくることが多いです。
この頃になると、首がすわり始め、周囲のものに興味を持ち始める次期です。授乳のリズムが整い、生活リズムも安定してきます。
また、夜間の授乳がなくなる赤ちゃんも増えてきます。ミルクの量も、かなり安定してくる傾向があり、授乳中に周りの音や動きに気を取られて集中できないことも出てくるかもしれません。
関連記事:ほほえみクラブ 生後3ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後4ヵ月
5ヵ月~6ヵ月
5ヵ月〜6ヵ月の赤ちゃんのミルクの量は、1回あたり180〜220ml程度になり、授乳間隔も4時間おき程度が基本ですが、離乳食の開始により変化します。
離乳食は、まず1日1回から始め、赤ちゃんの様子を見ながら徐々に回数を増やしていきます。離乳食から栄養を摂る量が増えるにつれて、ミルクの量は少し減るか、横ばいになることが多いでしょう。
離乳食のあとにミルクをあげるか、ミルクのあとに離乳食をあげるかは、赤ちゃんの食欲や離乳食の進み具合によって調整します。
この頃からミルクは主要な栄養源から、補助的な水分・栄養源へと役割が変化していきます。
関連記事:ほほえみクラブ 生後5ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後6ヵ月
7ヵ月~8ヵ月
7ヵ月〜8ヵ月の赤ちゃんのミルクの量は、1回あたり180〜200ml程度が目安ですが、離乳食の進み具合で大きく変わります。
この頃には離乳食が1日2回になることが多く、ミルクは離乳食の合間や食後に与えることが多くなります。
そのため、ミルクの量は離乳食の摂取量に応じて調整しましょう。この頃になると、哺乳瓶以外のコップやストローマグで水分補給を始める練習も取り入れられます。ミルクの回数は1日3〜4回程度に減ってくることが多いでしょう。
関連記事:ほほえみクラブ 生後7ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後8ヵ月
9ヵ月~11ヵ月
9ヵ月~11ヵ月の赤ちゃんのミルクの量は、1回あたり160〜200ml程度が目安ですが、離乳食がメインになります。離乳食が1日3回になるため、ミルクは離乳食の補助的な役割となります。
この時期になると、離乳食が完了期に近づき、ほとんどの栄養を食事から摂れるようになります。そのため、ミルクの回数は1日2〜3回程度に減らすのが一般的です。
食後の水分補給や、寝る前の習慣としてミルクを与える家庭も多く見られますが、ミルクの量よりも、バランスの取れた食事をしっかり摂れているかが大切です。赤ちゃんの成長や食欲に合わせて、無理なく移行していきましょう。
また以下の記事で3回食の食べさせ方や調理方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
関連記事:3回食の食べさせ方・調理方法
関連記事:ほほえみクラブ 生後9ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後10ヵ月
関連記事:ほほえみクラブ 生後11ヵ月
新生児(赤ちゃん)がミルクを飲まない原因
生まれたばかりの赤ちゃんがミルクを飲んでくれないと、保護者の方はとても心配になりますよね。新生児がミルクを飲まない原因はいくつか考えられます。
授乳環境が整っていない
赤ちゃんは非常に敏感です。授乳環境が落ち着かないと、集中してミルクを飲むことが難しくなります。
室内の照明が明るすぎる・音がうるさい
部屋が明るすぎたり、テレビや周りの話し声が大きかったりすると、赤ちゃんが集中できないことがあります。静かで落ち着いた環境で授乳するように心がけましょう。
姿勢が悪い
抱き方が不安定だったり、赤ちゃんの首が反りすぎていたりすると、ミルクをうまく飲むことができません。赤ちゃんがリラックスして飲めるような安定した姿勢を見つけてあげましょう。縦抱きや横抱きなど、いろいろな抱き方を試してみるのもよいでしょう。
温度が適温でない
部屋の温度が暑すぎたり寒すぎたりすると、赤ちゃんは不快に感じて飲まなくなることがあります。赤ちゃんが快適に過ごせる適温(夏場は25〜27度、冬場は20〜23度程度)に保ちましょう。
お母さんが焦っている
授乳はお母さんと赤ちゃんがゆっくりと向き合う時間です。焦らず、落ち着いた気持ちで授乳に臨むことが大切です。
ミルクの温度が適温になっていない
ミルクの温度が暑すぎると、赤ちゃんの口のなかをやけどさせてしまう危険があるだけでなく、熱すぎると嫌がって飲んでくれません。熱いと感じる場合は必ず冷ましてから与えましょう。
またミルクの温度が冷たすぎると嫌がることが多いうえ、消化に負担がかかる可能性があります。
ミルクの適温は、人肌程度(約37度)が適温とされています。ミルクを混ぜたあと、清潔な手の甲に数滴垂らして温かくも冷たくもないと感じるくらいがちょうどよいでしょう。
哺乳瓶の乳首が合っていない
哺乳瓶の乳首は素材や形状、穴の大きさなどさまざまな種類があります。
穴が小さすぎると、赤ちゃんが吸ってもなかなかミルクが出てこないため、疲れて途中で諦めてしまうことがあります。
また穴が大きすぎると、ミルクが出すぎてしまい、赤ちゃんがむせたり、飲み込むのが追いつかずに嫌がったりすることがあります。
素材や形状においても、シリコン製やゴム製、さまざまな形状の乳首があります。赤ちゃんの口に合うもの、吸いやすいものを見つけるためにいくつか試してみるとよいでしょう。
体調不良
赤ちゃんが普段と比べてミルクを飲まない場合、体調不良のサインである可能性も考えられます。
発熱
熱があるときは、食欲が落ちることがよくあります。体力を消耗するため、授乳量も減りがちです。
鼻づまり
鼻が詰まっていると呼吸が苦しくなり、ミルクを吸うのが難しくなります。鼻吸い器でこまめに鼻水を取ってあげましょう。加湿器を使用したり、蒸しタオルを鼻に当てて温めたりするのも効果的です。
口内炎や舌苔(ぜったい)
口のなかに痛みがあったり、舌に白い苔状(こけじょう)の舌苔が厚くついていたりすると、不快感でミルクを嫌がることがあります。口の中を清潔に保つよう心がけ、症状が続く場合は小児科を受診しましょう。
消化器症状
下痢や嘔吐がある場合は胃腸の調子が悪く、ミルクを受けつけないことがあります。脱水症状に注意して少量ずつ頻繁に水分補給を試みましょう。
中耳炎
耳の痛みがある場合、ミルクを吸う動作で耳に圧力がかかり、痛みが強くなるため、飲まなくなることがあります。耳を触る仕草や不機嫌が続く場合は耳鼻科の受診も検討しましょう。
その他
いつもと様子が違う、ぐったりしている、機嫌が悪いなどの症状をともなう場合は、早めに小児科を受診しましょう。
ミルクの量が足りているときの新生児の様子
赤ちゃんがミルクをしっかり飲めているか、足りているかどうかは、保護者の方にとって一番の心配事かもしれません。特に新生児期は体重増加が非常に重要です。以下の項目を参考にミルクが足りているかを確認してみるとよいでしょう。
体重が増えている
最も確実で客観的なサインは体重が順調に増えていることです。
新生児期は1日あたり20~30g程度の体重増加が目安とされています。生後2週間頃には出生時の体重に戻っていることが理想的です。
順調に体重が増えているかどうかは、定期的に母子手帳に記載されている発育曲線に沿って体重が増えているかを確認しましょう。乳児健診や地域の保健センターなどで体重測定をしてもらうのもよいでしょう。
機嫌がよい
ミルクが足りていてお腹が満たされている赤ちゃんは、機嫌がよいことが多いです。
授乳後しばらくは満足して眠っていたり、手足を活発に動かして遊んだり、あやされると笑顔を見せたりします。泣いている時間が短く、泣いても抱っこや声かけで比較的すぐに落ち着くようであれば、お腹が満たされているサインです。
1日におしっこが6回以上出ている
ミルクがしっかり飲めていれば、おしっこの量も十分に確保されます。
新生児期は、1日あたり6回以上、おむつがずっしりと重くなるくらいのおしっこが出ていれば、水分が足りているサインです。
もし、おしっこの回数が少ない、おむつが軽いと感じる場合は、水分不足の可能性を疑いましょう。
肌に透明感・弾力がある
ミルクが足りていると、赤ちゃんの肌に透明感があり、触るとふっくらとして弾力がある状態です。
指で軽く押してみて、すぐにもとに戻るようであれば、脱水の心配は少ないでしょう。唇や口の中が潤っているかどうかも確認しましょう。これらのサインが見られれば、赤ちゃんは十分なミルクを摂取できていると考えてよいでしょう。肌が乾燥していたり、弾力がなかったりする場合は、水分が不足している可能性があります。
ミルクの量が足りていないときの新生児の様子
ミルクの量が足りていない場合、赤ちゃんは以下のようなサインを見せることがあります。これらのサインが見られた場合は、早めに小児科医や助産師に相談しましょう。
体重が増えない
最もわかりやすいサインは体重の増加が思わしくないことです。
新生児期に1日あたり20g未満の増加が続く場合や、出生時の体重になかなか戻らない場合は、ミルクが足りていない可能性があります。
また、定期的な体重測定で成長曲線から大きく外れていたり、横ばいが続いたりする場合は注意が必要です。体重が減り続けている場合は速やかに医療機関を受診してください。
1日におしっこが5回未満しか出ていない
水分摂取量が少ないと、おしっこの回数や量が減ります。
1日のおしっこの回数が5回未満である場合やおむつがほとんど濡れていないと感じる場合は、ミルクが足りていない可能性があります。
また、おしっこの色が濃い黄色であったり、匂いがきつかったりする場合も水分不足のサインかもしれません。おしっこの回数が少ない状態が続く場合は脱水のリスクが高くなります。
便秘気味でうんちが硬い
ミルクの量が足りないと便の量も少なくなり、便秘になることがあります。
うんちの回数が少ないだけでなく、うんちが硬く、コロコロしている場合や、排便時に赤ちゃんが苦しそうにしている場合は、ミルク不足による便秘の可能性があります。
普段のうんちの状態と比較して、明らかに変化がある場合は注意しましょう。また、うんちの色がいつもと違う、血が混じっているなどの場合は、すぐに医療機関を受診してください。
これらのサインが見られた場合は、ミルクの量や授乳方法の見直しが必要かもしれません。自己判断せず、小児科医や保健師に相談して適切なアドバイスを受けるようにしてください。
新生児にミルクをあげる際の注意点
赤ちゃんにミルクをあげる際にはいくつかの大切な注意点があります。これらに注意することで赤ちゃんが安全に、そして快適にミルクを飲むことができます。
授乳を始める前に、体調や乳房に変化がないか確認する
授乳は赤ちゃんだけでなくお母さんの体調にも影響します。
授乳前にはお母さん自身が体調を崩していないか、熱がないかなどを確認しましょう。赤ちゃんへの感染を予防するためにも大切です。体調が優れないときは無理をせず、パートナーや家族に協力を求めましょう。
また、乳房が張っていないか、乳首に傷がないか、乳腺炎の兆候がないかなどの確認も大切です。乳腺炎の初期症状(乳房の痛み、熱感、しこりなど)があれば授乳前に軽く搾乳したり、冷やしたりするなどの対処が必要です。痛みなどが強い場合は、医療機関に相談しましょう。
ミルクは作り置きしない
調乳したミルクは時間の経過とともに細菌が繁殖しやすくなります。
そのため、ミルクは赤ちゃんが飲む直前に必要な量だけ調乳するのが基本です。
調乳後のミルクは冷蔵庫に入れても長時間保存できません。衛生上のリスクがあるため、飲み残しは捨てて作り置きは避けましょう。
どうしても作り置きが必要な場合は、調乳後すぐに冷蔵庫に入れ、1時間以内に使い切るようにしましょう。外出時など、やむを得ず持ち運ぶ場合は、保温できるボトルに入れるなどして、できるだけ早く与えるように心がけましょう。
関連記事:ほほえみクラブ 【看護師監修】赤ちゃんの粉ミルクを作り置きする場合はどうする?作り置きをする際の注意点について
参照:厚生労働省/「乳児用調製粉乳の安全な調乳、保存及び取扱いに関するガイドラインの概要」
ミルクをあげる間隔が短い場合は量を増やす
赤ちゃんが頻繁にミルクを欲しがる場合は現在のミルクの量が足りていない可能性があります。
授乳後すぐに泣き出す、間隔が短いのにまた欲しがる、授乳中もずっと吸い続けているなどのサインは、もっとミルクが欲しいという赤ちゃんのメッセージかもしれません。
このような場合は1回あたりのミルクの量を少し増やしてみましょう。例えば、普段80mlあげているなら90ml、100mlと少しずつ増やしてみて、赤ちゃんが満足する量を見つけていきます。
無理強いはしない:
赤ちゃんが嫌がっているのに無理に飲ませることは避けましょう。赤ちゃんのペースを尊重することが大切です。
量を増やしても頻繁に欲しがったり、体重増加が思わしくなかったりする場合は、かかりつけの小児科医や保健師に相談して適切なアドバイスを受けましょう。
赤ちゃんの成長に合わせたミルクをあげよう
赤ちゃんのミルクの量や間隔は成長とともに変化していきます。本や商品に書かれている量はあくまで一般的な目安であり、赤ちゃん一人一人の個性や体調、成長のペースに合わせて柔軟に対応していくことが何よりも大切です。
ミルクを飲んだあとの赤ちゃんの機嫌、おしっこやうんちの回数と量、そして体重の増え方など、日々の変化を注意深く観察しましょう。これらは、赤ちゃんがミルクを十分に摂取できているか、あるいは足りていないかを示す大切なサインです。
「これでいいのかな?」「うちの子は他の子と違う?」と不安に感じたり、判断に迷ったりしたときは、一人で悩まずに、かかりつけの小児科医や助産師、地域の保健師など、専門家に遠慮なく相談してください。ミルクだけでなく、母乳と混合で育児をしている場合も、赤ちゃんの体重増加や排泄の状況をよく見てミルクの量を調整していくことが大切です。母乳の分泌量とミルクの量のバランスを考慮し、赤ちゃんが無理なく成長できるようサポートしましょう。
育児は毎日が発見と学びの連続です。特に新生児期は、赤ちゃんも保護者の方もお互いに慣れていく大切な時期です。日々の育児で疲れることもあると思いますが、完璧を目指すのではなく、赤ちゃんとのコミュニケーションを楽しみながら育児に取り組んでいきましょう。
明治では、計量不要のキューブタイプやそのまま使える液体タイプの乳児用ミルク「明治ほほえみ」を用意しています。使いやすさにも栄養設計にもこだわり、赤ちゃんが自ら育つ力に寄り添います。忙しいときや大変なときに、ぜひこれらの商品をご活用ください。