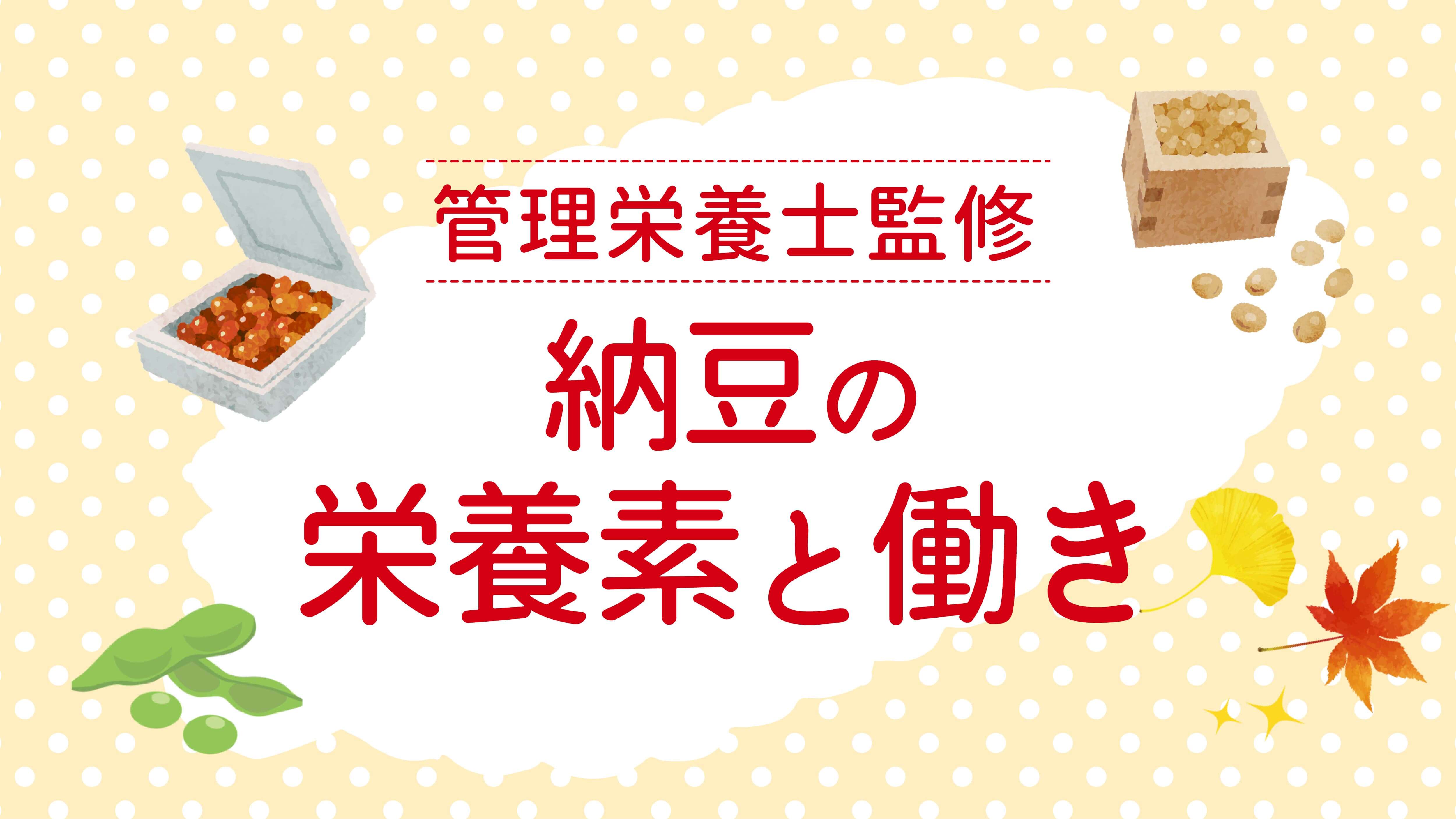納豆は、パックを開けるだけで簡単に食べられる便利な食品です。発酵過程を経ることで栄養価が高まり、健康維持にも役立つ成分を豊富に含むため、毎日の食事に取り入れたくなる食品でもあります。また、腸内環境を整える「プロバイオティクスを含む食品」としても知られており、腸活にも役立つと注目されています。
この記事では、納豆に含まれる栄養素とその働き、上手な取り入れ方や取り入れる際の注意点について解説します。

この記事の執筆者
管理栄養士
横川 仁美
管理栄養士の資格を取得後、保健指導や重症化予防を中心に2500人以上へのアドバイスを行ってきた。現在は、管理栄養士、食専門ライター、料理研究家として、執筆、商品監修、レシピ開発などを行っている。健康食育シニアマスターの資格を持つ。

この記事の監修者
内科医・医学博士・桜の咲クリニック院長
岡庭 紀子
桜の咲クリニック院長。医学博士。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本内視鏡学会内視鏡専門医。愛知医学大学医学部卒業後、愛知医科大学消化管内科入局。愛知県内のクリニックに勤務後、 桜の咲クリニックを開院。クリニックでは腸活やメディカルファスティング(ダイエット)など生活習慣の指導も行う。
納豆に含まれる主な栄養素
納豆は、蒸した大豆に納豆菌を加えて発酵させた日本の伝統食品です*1。発酵過程を経ることで、大豆由来の栄養素がより消化吸収されやすくなり、ビタミンも増加します*2*3。
下記に納豆に含まれる特徴的な栄養素とその働きについて紹介します。
▼納豆に含まれる栄養素*3
| 栄養成分 | 納豆(可食部100g当たり) |
|---|---|
| たんぱく質 | 16.5g |
| 食物繊維 | 9.5g |
| ビタミンK | 870μg |
| ビタミンB2 | 0.30mg |
| 葉酸 | 130μg |
たんぱく質

納豆は大豆を原料としているため、植物性たんぱく質を豊富に含んでいます*3。たんぱく質は体の組織や筋肉をつくるために欠かせない栄養素です。大豆にはたんぱく質を構成しているアミノ酸のうち、体内で生合成できない9種類の必須アミノ酸がバランス良く含まれており、植物性たんぱくの中でも良質なたんぱくとされています*4。
食物繊維

食物繊維は、水溶性と不溶性の2種類があります。水溶性食物繊維は、消化管での糖の吸収を遅らせ、急激な血糖値の上昇を抑える働きがあります*5。一方、不溶性食物繊維は便の量を増やし、腸を刺激して腸の動きを活発にします*5。納豆には、この両方の食物繊維が含まれています*3*6。
ビタミンK
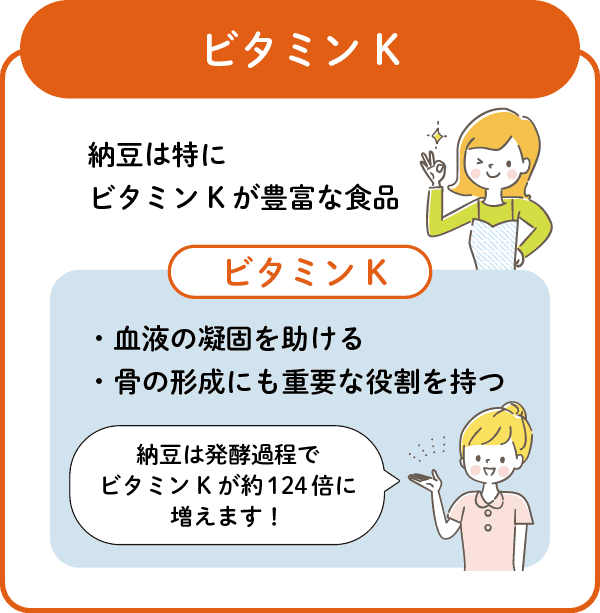
ビタミンKは血液の凝固を助けるだけでなく、骨の形成にも重要な役割を果たします*7。納豆は発酵過程で、大豆に含まれるビタミンKが約124倍に増えるため、特にビタミンKが豊富な食品として知られています(黄大豆・茹で100g当たり7μg→糸引き納豆では870μg)*2*3。
ビタミンB2
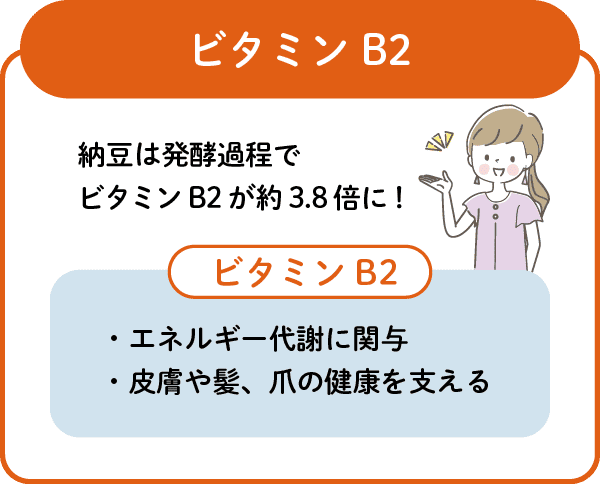
ビタミンB2はエネルギー代謝に関与し、皮膚や髪、爪の健康を支える働きがあります*8。納豆は発酵過程で、大豆の約3.8倍のビタミンB2を含むようになります(黄大豆・茹で100g当たり0.08mg→糸引き納豆では0.30mg)*3。
葉酸

葉酸は細胞の増殖に欠かせないDNAやRNAの合成に関与し、特に胎児の正常な発育に重要な栄養素です。女性においては妊娠前から産後にかけての摂取が推奨されています*9。納豆の発酵過程で、葉酸も大豆に比べて約3倍多く含まれるようになります(黄大豆・茹で100g当たり41μg→糸引き納豆では130μg)*3。
大豆イソフラボン

納豆は大豆を主原料としているため、大豆イソフラボンを含んでいます。この成分は、女性ホルモン「エストロゲン」に似た構造をしており、体内でエストロゲンと似た働きをすることで知られています*10。
ナットウキナーゼ

納豆に特有の成分として注目されるナットウキナーゼは、大豆を納豆菌で発酵させる過程で生成される酵素です*2。大豆には含まれていない成分で、血栓を分解する作用があると言われています*11。
*1 農林水産省 子どもの食育「食材を知ろう!大豆編」
*2 三星沙織. 納豆. 日本調理科学会誌(J. Cookery Sci. Jpn.), 2019, Vol. 52, No.1, p.33~37
*3 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年・ 第2章(データ)糸引き納豆及び全粒 黄大豆 国産 ゆで」
*4 公益財団法人日本豆類協会「豆の主な栄養素」
*5 株式会社明治 Hello. Chocolate「食物繊維の多い食べ物は?効果的に摂取してお腹の調子を整えよう」
*6 文部科学省「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年・第2章本表別表1(データ)糸引き納豆参照 」
*7 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書 ビタミン(脂溶性ビタミン ➃ビタミンK」p192
*8 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書 ビタミン(水溶性ビタミン)②ビタミン B2」p214
*9 厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)策定検討会報告書 ビタミン(水溶性ビタミン)⑥葉酸」p232,234,236,237
*10 厚生労働省 「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」
*11 Kazonobu Omura, et al. Fibrinolytic and anti-thrombotic effect of NKCP, the protein layer from Bacillus subtilis (natto). Biofactors. 2004;22(1-4):185-7.
納豆の健康効果

腸内には善玉菌や悪玉菌をはじめとする多様な菌が共存しており、複雑に影響し合いながらバランスを保っています。腸内の健康を維持するためには、乳酸菌などの善玉菌の割合を高めることが重要です*12。納豆に含まれる「納豆菌」は、胃酸に耐えて腸まで生きたまま届き、ビフィズス菌や乳酸菌の増殖を促進する「プロバイオティクス」として広く知られています*12*13。
さらに、最近の研究では、大豆を使用した加工食品や発酵大豆製品(納豆)が腸内環境だけでなく生活習慣病や心疾患に良い影響を与える可能性があることが報告されています*13*14。
納豆加工品摂取による腸内細菌叢の変動

納豆加工食品の摂取により、有用な腸内細菌が増加することが確認されました。ただし、その増加の程度は、摂取前の腸内細菌の状態や食生活によって異なることも明らかになりました。本研究の結果から、腸内細菌叢の改善を目指す場合、事前に腸内細菌叢の状態を把握し、その状態に応じて適切な食品を選択することが重要であることが示唆されました*13。
大豆および発酵大豆製品の摂取と死亡率との関連

大豆および発酵大豆製品(納豆や味噌)の摂取と総死亡率および原因別死亡率との関連についても注目されています。日本の大規模な研究において、大豆製品全体での摂取量と総死亡率には有意な関連性は見られなかったものの、発酵大豆製品(納豆や味噌)では、男女ともに摂取量と総死亡率の低下に関連性があることが示されました。特に納豆は心血管疾患による死亡率を低下させる可能性があり、発酵大豆製品の摂取が健康に良い影響を与える可能性があることが示唆されています*14。
*12 厚生労働省 健康日本21アクション支援システム「乳酸菌」
*13 Kanako Kono, et al. Fluctuations in Intestinal Microbiota Following Ingestion of Natto Powder Containing Bacillus subtilis var. natto SONOMONO Spores: Considerations Using a Large-Scale Intestinal Microflora Database. Nutrients, 2022, vol.14, no.18, p.3839.
*14 Ryoko Katagiri et al., Association of Soy and Fermented Soy Product Intake with Total and Cause Specific Mortality: Prospective Cohort Study. BMJ, 2020, vol. 368,
納豆の上手なとり方
納豆を日常生活に上手に取り入れるためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。
毎日の習慣として取り入れる

発酵食品に含まれるプロバイオティクスは、食べ物から摂取しても一時的にしか体内にとどまらないため、毎日摂取することが大切です。習慣的に納豆を食事に取り入れましょう。
発酵食品には、納豆以外にもヨーグルト、乳酸菌飲料、漬物などがあり、これらをバランス良く食事に取り入れることで、腸内の健康に役立つことが期待できます*12。
食物繊維をプラスして腸活を強化!
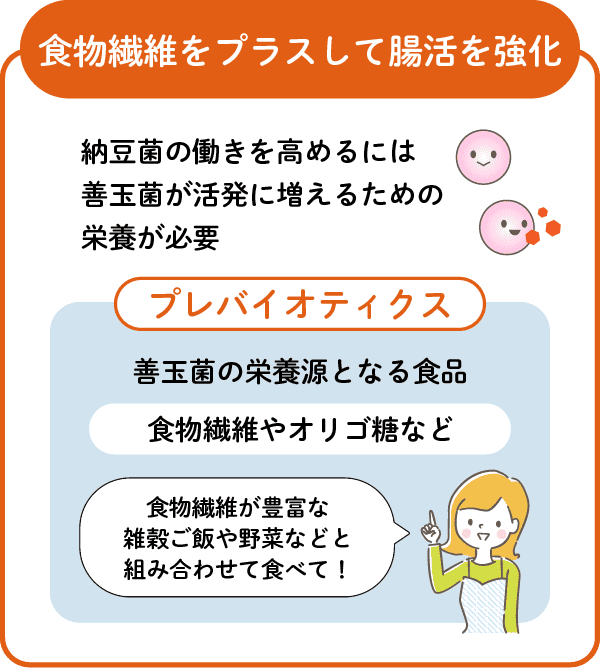
納豆に含まれる納豆菌(プロバイオティクス)の働きを高めるには、腸内の善玉菌が活発に増えるための栄養が必要です。その栄養源が食物繊維やオリゴ糖であり、これを「プレバイオティクス」と呼びます*12*13。 納豆には食物繊維も含まれていますが、さらに食物繊維が豊富な雑穀ご飯や野菜などと組み合わせて食べることで、納豆菌と食物繊維を同時に摂取することができます*3。
納豆を食べるおすすめのタイミング|朝と夜どっち?

納豆はどのタイミングで食べてもよいですが、朝と夜に食べるそれぞれのメリットを紹介します。
腸活を意識して納豆を食べる場合は、朝食時がおすすめです。朝食をとることで胃腸の蠕動(ぜんどう)運動を促進し、腸の動きが活発になりますが、その中でも朝食に納豆にも含まれている食物繊維を摂取することで便通症状が改善したという研究があります*15。
生活習慣病が気になる人は納豆は夜に食べるのがおすすめです。納豆に含まれるナットウキナーゼには血栓を溶かす作用がありますが*11、その効果はナットウキナーゼ摂取後6~8時間にわたり持続することが報告されています*16。血栓は就寝時など活動の少ないときにつくられやすく*17、ナットウキナーゼの血栓を溶かす効果を発揮させるためには夜に食べるのがよいでしょう。
*15 Kim Hyeon-Ki et al., Ingestion of Helianthus tuberosus at Breakfast Rather Than at Dinner Is More Effective for Suppressing Glucose Levels and Improving the Intestinal Microbiota in Older Adults.Nutrients. 2020 Oct 3;12(10):3035. doi: 10.3390/nu12103035
*16 Kurosawa Y et al., A single-dose of oral nattokinase potentiates thrombolysis and anti-coagulation profiles. scientific reports. 2015, 5:11601
*17 一般社団法人 日本血栓止血学会「血栓症ガイドブック」
納豆を食べるときの注意点
納豆には多くの栄養素が含まれ、健康維持に役立つ食品ですが、食べ過ぎると栄養バランスが偏る可能性があります。栄養を効果的に取り入れるためには、さまざまな食材を組み合わせることが大切です。
1日1パックを目安に

納豆の適量には明確な基準はありませんが、大豆イソフラボンの1日摂取上限は70~75mg(アグリコン換算)とされています*18。納豆1パック(45g)には約33mgの大豆イソフラボンが含まれており、1日2パックになると他の食事でのイソフラボン量も含めて上限を超える可能性があるため、1日1パック程度に抑えることが望ましいでしょう。
また、たんぱく質は肉や魚、たまご、乳製品からも補えますので、バランスの良い食事を心がけることが大切です。健康のためには、特定の栄養素だけに偏らず、さまざまな食品からバランス良く栄養をとることが重要です。
※アグリコン換算について:食品中の大豆イソフラボンは通常、糖と結びついた形で存在し、腸内で糖が分解されてアグリコンという形で吸収されます。そのため、食品に含まれるイソフラボン量はアグリコン換算で表されることが一般的です*18。
薬によっては注意が必要

ワルファリンという薬を服用している人は、納豆を食べる際に注意が必要です。ワルファリンは、血液を固まりにくくし、血栓を防ぐ薬です。ワルファリンはビタミンKの働きを抑えて働きますが、納豆はビタミンKが豊富に含まれるため、納豆に含まれるビタミンKが薬の働きを弱めてしまう可能性があります。納豆菌の発酵過程でビタミンKが生成されるため、納豆にはビタミンKが豊富に含まれるといえます。ワルファリンを服用している人は、納豆の摂取について医師または薬剤師に相談することをおすすめします*19。
*18 食品安全委員会 「大豆及び大豆イソフラボンに関するQ&A」
*19 独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)「Q3 ワルファリンを飲んでいますが、納豆、クロレラ、青汁などの摂取を避けるように指導されました。なぜ、食べてはいけないのですか?」
まとめ
今回の記事では、納豆に含まれる栄養素とその働きについて解説しました。納豆はたんぱく質やビタミンK、食物繊維、大豆イソフラボン、ナットウキナーゼなど、さまざまな栄養素を含んでいます。また、腸内環境を整えるプロバイオティクスを含む食品としても注目されています。しかし、栄養バランスを保つためには、ほかの食材と組み合わせて取り入れることが重要です。特に薬を服用している人は、医師に相談した上で摂取を検討することが推奨されます。
合わせて読みたいおすすめ記事
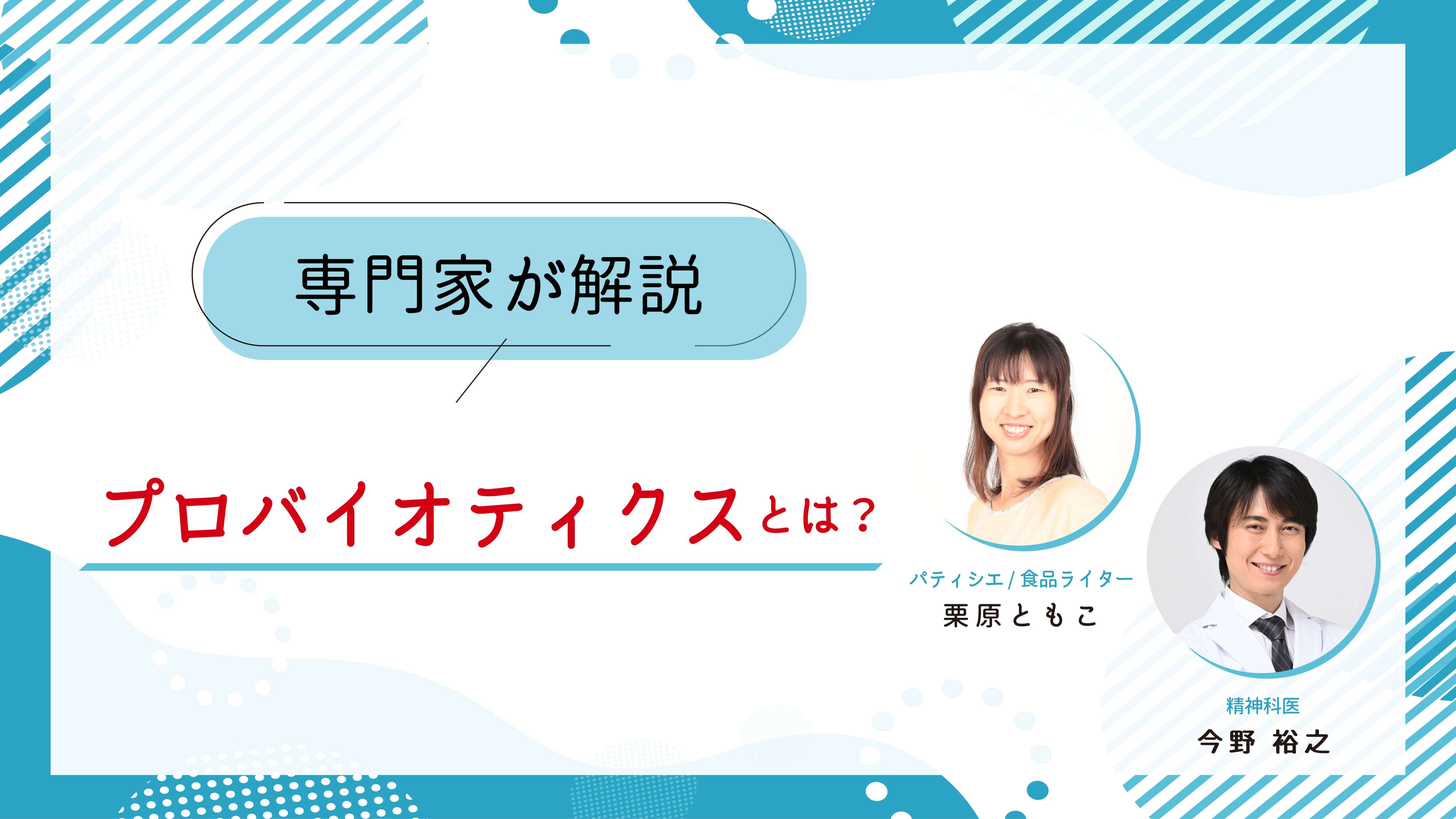
プロバイオティクスとは?効果と種類・おすすめの食品・とり方のコツを紹介
善玉菌を育てるのに有効なプロバイオティクス。腸内フローラを整えるのに役立つと言われていますが、プロバイオティクスとは何のことなのでしょうか?この記事ではプロバイオティクスの種類とその働き、プロバイオティクスを含むおすすめの食品、プレバイオティクスとの違いについて紹介します。
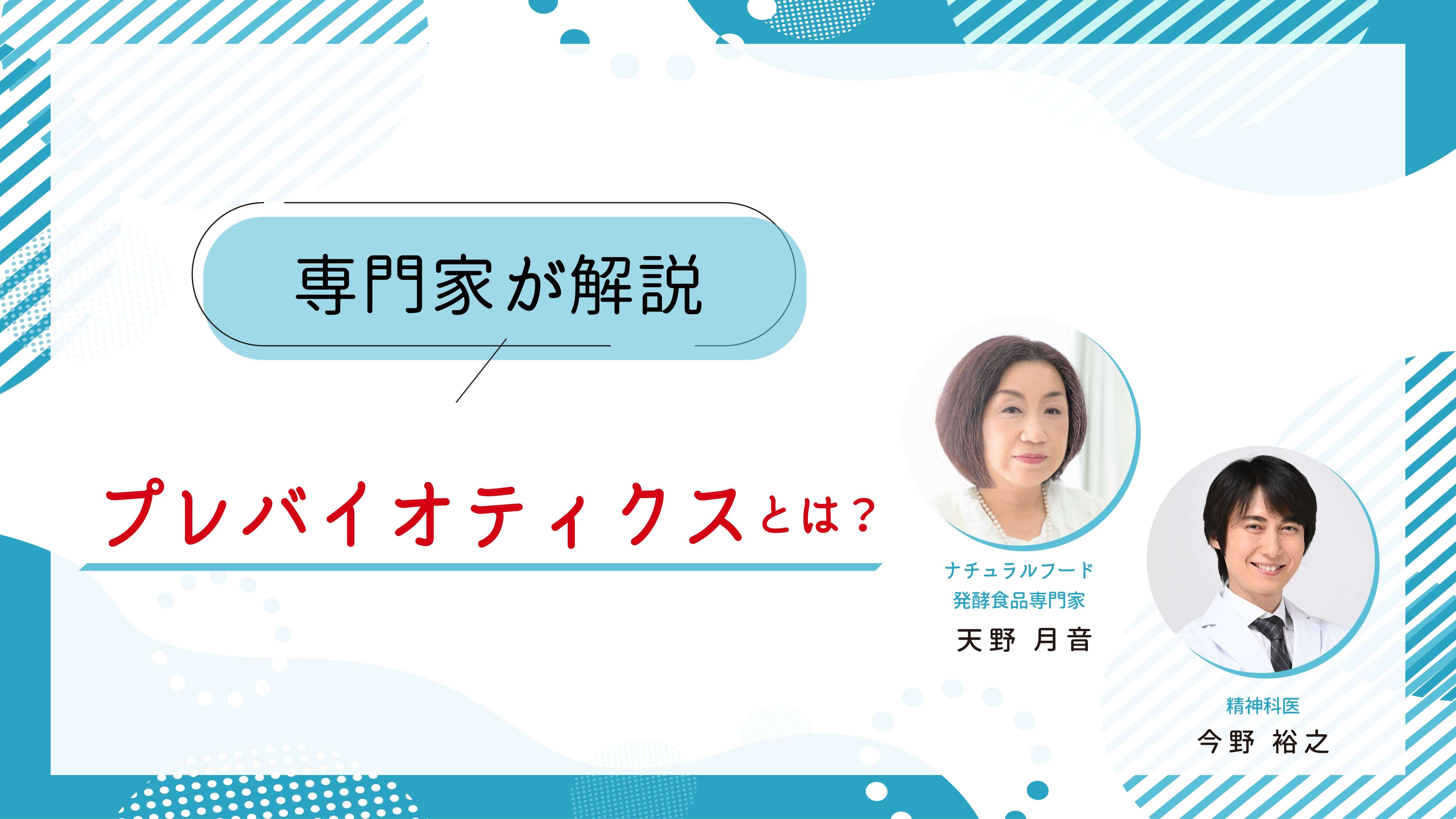
プレバイオティクスとは?健康効果や食品例、効果的なとり方を解説
善玉菌を増やし、腸内環境を整えながら健康をサポートするプレバイオティクス。善玉菌のエサとなり、腸内環境を整えるのに有効と考えられています。今回はプレバイオティクスの効果や食品例、効果的なとり方について解説します。

オリゴ糖を含む食べ物と上手に取り入れる方法
腸内環境を整え、健康をサポートするオリゴ糖が注目されています。オリゴ糖は腸内の善玉菌を増やす働きだけでなく、血糖値の上昇抑制やむし歯予防にも役立つと言われています。この記事では、オリゴ糖を含む食べ物と、日常生活に無理なく取り入れる方法を紹介します。

納豆が腸活におすすめのワケ|効果的な食べ方と腸活納豆レシピを紹介
納豆は腸活におすすめの発酵食品です。今回は納豆が腸活に効果的な理由や、効果的な食べ方を解説します。効果を高めるおすすめ食材との組み合わせや納豆を使った簡単腸活レシピも紹介しているので参考にしてみてください。